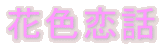
―小さな花屋の物語―
第15話
「頼むっ、親父頼む!」
「うるせえっ! んなことできるわけねえだろがっ」
閉店間際の沢村酒店に、怒号が響き渡る。しかし隆矢は臆することなく、ひたすら床に額をこすり付けて懇願する。
「費用は全て俺が出す。一度に全部は無理でも、これからここで働かせてもらって、その給料から少しずつ返す。必ず返す。だから頼むっ」
「黙りやがれ、このボンクラ息子っ。家業を馬鹿にして出て行って、いきなり帰ってきたと思ったら無茶苦茶なこと頼みやがって。大体なあ、てめえは勘当されてんだぞ。どのツラ下げて戻ってきやがったんだッ」
隆矢に反論などできるはずもない。全て父の言う通りなのだから。ただ頭を下げて、頼み込むしかないのだ。
「親父の言う通り、俺は本当にどうしようもないバカだ。柾矢の気持ちも親父たちの気持ちも、何にも分かっちゃいなかった。我がままなガキのまんま、色々なことから顔を背けて好き勝手やってきた………」
板張りの廊下にがりがりと爪を立て、込み上げる嗚咽をこらえる。今は泣いている時ではない。
「親父が俺を許せないのも、信用できないのも当然だ。だからこそ頼む。もう一度チャンスをくれ。俺を試してくれ。俺は柾矢のようにはできねえ。でも、俺なりのやり方で店のため、楓町のために頑張りたいんだ」
「はッ、綺麗ごと言いやがって」
土下座する息子の後頭部を見下ろしながら、徹矢は吐き棄てる。しかしその表情は苦悶に歪んでいた。彼も迷っていたのだ。
「……ここで働きたいっつうんなら、まあバイトとして雇ってやってもいい。しかしその突拍子もねえ頼みは聞き入れられねえな」
ここまではっきり言えば、隆矢も諦めるだろうと踏んでいた。それに、店に戻ってもいいと譲歩してやったのだし。しかし、
「頼む……俺は……これからもずっと、あいつの傍にいてやりたいんだ………」
そして床に額を押し付けたまま、
「聞き入れてくれるまで、俺はここをどかねえ。ぶっ倒れるまで土下座し続けてやる」
徹矢はくるりと背を向けて、
「はッ、知るか。ぶっ倒れちまえ」
ばしっと音を立てて戸を閉め、畳敷きの居間にどっかりと胡坐をかいた。
「あの子、柾矢より頑固ですよ」
妻の言葉にふいと顔を背けて、頭をがりがり掻く。言われなくても分かっていた。優柔不断なところも大いにあるが、それは決意を固めるまでのこと。いったんこうと決めたら梃子でも動かない。それが隆矢だった。
だからその翌朝、のっそり起き出して布団を畳み、居間の戸を開けた時、昨夜と同じ場所に同じ姿勢で土下座している息子の姿を見ても、徹矢は驚かなかった。チッと忌々しげに舌打ちすると、
「バカの一念、岩をも通す、か」
そう呟いて嬉しいような困ったような笑みを浮かべた。
「もうすぐクリスマスかあ………」
ナースステーションの窓口に、小さなクリスマスツリーが飾られていた。ふとカレンダーを見れば、12月ももう半ば過ぎ。店舗の明け渡しや引越し、そして父の転院手続きなどで忙しく、あっという間に時間が過ぎていった。
1年のうちで最も商店街が華やぐ季節。店ごとに飾り付けられたイルミネーションを眺めて歩くだけでわくわくする、優里の大好きな季節だったけれど、今年はそんな余裕もない。
店を畳んで以来、商店街には足を運んでもいなかった。
しかし淋しいとは思わなかった。寧ろ、忙しくてよかった。余計なことを考えずに済んだから。
有栖川は引越しを手伝ってくれたり、何度か会う機会はあった。お見舞いにも来てくれた。しかし隆矢とは、あの公園で別れて以来一度も逢っていない。
引っ越した小さなマンションでひとり、夜を過ごしている時など、逢いたくて逢いたくて叫び出しそうになる。
ううん、逢えなくてもいい。ただ声が聞ければ、優里がんばってるかと、あのあったかい声に触れることができればそれだけで―――
「優里っ………」
背後から名を呼ぶ声がして、優里はひくんと肩を震わせた。荒い呼吸で乱れているが、この声の主を間違うはずもない。
でもすぐに振り向かなかったのは、きっと幸せな幻聴に違いないと思ったから。これまでも、こういうことは何度かあったのだ。しかし、
「優里、久しぶりだな……」
「お兄…ちゃん……」
おそるおそる振り返ると、この階まで駆け上がってきたのか、息を切らせた隆矢の姿が。しかも―――
「お兄ちゃん、どうしたの? その格好……」
隆矢は頬にかかるほど長かった前髪を切り、藍地に白で沢村酒店と大きく書かれた前掛けをしていた。
しかし、優里の戸惑いを無視して隆矢はその腕を掴み、
「一緒に来て欲しい。お前に見せたいものがあるんだ」
「え……今から?」
隆矢は無造作に頷いて、腕を強引に引っ張る。優里は訳が分からなかったが、隆矢の真剣な眼差しに惹かれて大人しく付いていった。
すると隆矢は病院の駐輪場に真っ直ぐ向かい、留めていたバイクを指差して「後ろに乗れ」と言う。そのバイクにも「沢村酒店」の文字が。
優里は渡されたヘルメットをかぶって座席にまたがり、前に座った隆矢の腰にそおっと腕を回す。逞しい背中の温もりが胸に響いて、甘い痛みをもたらした。
「しっかり掴まってるんだぞ」
優里が答えるより早く、バイクは走り出した。どこへ行くのかと思っていたら、そのまま真っ直ぐ楓町商店街へ。
何がなんだか分からぬままバイクから降り、手を引かれて連れて行かれたのは他ならぬ沢村酒店。しかしそこには―――
「な…に……ここ………」
沢村酒店の一画が改築され、そこには小さな小さな―――花屋ができていた。
優里は溢れんばかりの芳香に引き寄せられるように、ふらふらと近付いてゆく。
「なんて……きれい………」
この3週間、家と病院の往復で、花と無縁の生活をしていた。それだけではない。今は父のリハビリに専念しようと、頭の中からも花を遠ざけていたのだ。
しかし今、こうして色とりどりの花たちを目の前にすると、自分がどれほど飢えていたか分かる。
ああ、僕はやっぱり花が好きなんだ、花屋の仕事が大好きなんだ―――
「ふふ……かわいい………」
小さな店だったけれど、クリスマスの飾り付けも完璧だった。トナカイを従えたサンタの人形が、<WELCOME>と書かれたプレートを掲げて笑っている。
肩に担いだ大きな袋の中には、どんなプレゼントが詰め込まれているのだろう。優里は、乾いていた心が徐々に潤ってゆくのを感じた。
しかし、本当の驚きはこれからだった。
隆矢は後ろからゆっくりと近付いて優里の肩に手を置き、
「お前の店だよ」
「………え?」
口を驚きの形にしたまま固まる優里の耳に唇を寄せ、隆矢はもう一度囁く。
「ここはお前の店だ」
「僕の……店? だって、だってここは―――」
そう、ここは紛れもなく沢村酒店。すると隆矢は照れ臭そうに鼻の頭を掻き、
「小さな店で構わない、お前はそう言ってたよな。ここだったら、俺も家業やりながら手伝うことができる。仕入れとか配達とか、力仕事なんかは俺がやるよ」
「家業って、お兄ちゃん………」
「ああ、俺は酒屋を継ぐよ。いや、まだまだ今は見習いだけど、必死に努力して店と商店街を盛り立てていきたい。そして優里、お前を……守りたい」
余りの出来事に、優里の繊細すぎる心はふぅっと遠のきかけた。今にも倒れそうによろめくが、隆矢の逞しく力強い腕に抱き留められて現実に還る。
「俺はどうしようもないバカだった。柾矢と比べられるのが恐くて、やらねばならないことは分かっていたのに、ずっと逃げ回っていたんだ」
ひとつひとつの言葉がじわじわと胸に浸透してゆく。優里は潤み始めた瞳を一心に向けて、隆矢の言葉に耳を傾ける。
「けれど、家業やこの商店街に注ぐお前の深い愛情が俺の目を覚ましてくれた。ありがとう。この店は、俺からのささやかな感謝のしるしだ。受け取ってくれるか?」
「お兄…ちゃ……ぼくぅ………」
腕の中で、涙を浮かべつつふるふると震える優里。隆矢は鳩尾から突き上げるような暴力的な愛情に翻弄されそうになったが、何とかこらえて懇願した。
「花屋のない楓町商店街は、淋しすぎる。優里、もう一度お前の魔法を見せてくれ」
言葉を超えた感動に突き動かされ、優里は何度も何度も頷く。そして迷うことなく隆矢の胸に飛び込んだ。
「ありがと………ふぇぇ………おにいちゃ……ありがとぉ…………」
ふかふかのセーターに頬擦りして、温かい涙を存分にしみ込ませる。隆矢はただ黙って頭や背中を撫でていたが、やがて優里の濡れた頬を手のひらでそっと包み込んで上を向かせ、
「俺だけの……力じゃねえんだよ………」
「え…?」
戸惑う優里に微笑みかけ、親指を突き立てて後ろを指す。つられて隆矢の背後を見ると、そこには楓町商店街の仲間たちが。
「改装費とか、こいつらもカンパしてくれたんだ」
「みんな…が?」
にやにや笑いながら相太が近付き、隆矢の頭をぱこっと叩く。
「俺らに何の相談もしねえで、一人で費用全部抱え込んでやろうとしてたんだぜ、こいつ。そんなキャラじゃねえくせに」
肉屋の三代目敦彦もそうだそうだと同調して、
「いきなり改装が始まってよ。何だと思ったらここに花屋を作るって。まったく、少しは俺らを頼れっつうの。それによ、優里は楓町商店街のマドンナなんだぜ。みんなのものなんだ」
「うるせ。優里は俺のだっ」
まるで当然のように返す隆矢。優里は思わずどきりとしたが、小さく頭を振って熱を散らした。
そう、そんな深い意味などない。それに、これ以上のものを望んだりしたら罰が当たるというもの。
しかし、そんな優里の思惑になど構うことなく、隆矢は腕の中を優里を渡すものかと言わんばかりにぎゅうっと抱き締める。その時、
「皆さんの仰る通りです。優里さんはあなただけのものではありませんよ」
深みのある落ち着いた声で諭されて、隆矢は不愉快を隠そうともせず睨み付ける。対照的に優里はぱっと顔を輝かせて、「有栖川さんっ」と叫びつつぱたぱたと駆け寄った。
「見てくださいっ。このお店。お兄ちゃんたちが作ってくれたの。素敵でしょう?」
頬を赤く染め、眩いほどの笑顔を浮かべて小さな小さなお店を紹介する。まるで、サンタにもらったプレゼントを得意げに見せる子供のように。
有栖川は、自然と綻ぶ口許を敢えてにやりと歪めて、
「ええ、とても素敵です。でも残念ながら、大事なものがひとつ足りない」
不思議そうに首を傾げる優里の目の前に、後ろ手に隠していたものをそっと差し出す。
「これは……」
「はい、お店の看板です」
木目が微かに浮き上がったアンティーク調の白木。中央に<FlowerShop MISONO>と彫られた看板は、大きさといい色調といい、優里の店にぴったり合っていた。
「有栖川さん……」
優里は震える手で受け取って、その愛らしい看板をじっと見つめた。有栖川はにっこり笑って、
「僕もあなたの魔法が見たいです。また、ここに花を買いに来てもいいですか?」
優里は秘めやかに潤んだ黒瞳を真っ直ぐ向けて頷き、
「一輪でもきれいにラッピングして差し上げます」
「ありがとう」
優里はにっこり微笑むと、看板を相太たちに見せびらかした。
「みてみてー、可愛い看板でしょ?」
「おお、店の雰囲気にぴったりだなぁ」
そんなやり取りを横目にしつつ、有栖川はすっと隆矢の傍に近寄って低い声で、
「今回は負けましたが、まだ諦めたわけではありませんからね。油断していると痛い目に遭いますよ」
物騒な宣戦布告を隆矢は正面から受け止めた。
「分かってる。あんたには渡さねえ」
優しい“お兄ちゃん”の顔ではなく、昏く暴力的な所有欲を秘めた“男”の顔で叩き付けた。
BACK TOP NEXT