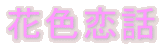
―小さな花屋の物語―
第16話(最終話)
「明日からは忙しくなるな」
隆矢はうんっ、と背伸びをして、隣の優里に笑いかける。花屋の新装開店を知らせるチラシを整理し終えた二人は、心地よい疲労感を味わっていた。
優里は上目使いで隆矢の顔を覗き込んで、
「お兄ちゃん、ごめんね。酒屋さんの仕事で疲れてるのに…………ん、んがっ………」
鼻をぎゅっとつままれた優里は、ふがふが言いながら手をぱたぱたさせた。
「お兄ちゃん、痛いよおっ」
「うるせ。いいか優里。そういう遠慮は優しさとは違うんだぞ。俺は部外者じゃない。お前と一緒にがんばって、一緒に生きていくんだ。だから疲れてるのにごめんとか、迷惑かけてごめんとか、そんなことは金輪際言うな。分かったな」
優里は泣き出しそうになるのを唇を噛んでこらえ、そして何度も何度も頷いた。隆矢はその頭をよしよしと撫でると、
「そんじゃ、ちょっと俺の部屋に行かねえか?」
「えっ? いいの?」
隆矢が自室に呼んでくれるなんて、何年ぶりのことだろう。優里は嬉しさの余りぴょんと勢いよく立ち上がって、「行くぅ」と無邪気に笑う。
隆矢は苦笑を浮かべつつ、少しは警戒しろよな…と独りごちた。
「お兄ちゃんのへっや、お兄ちゃんのへっや♪」
優里は謎の歌を口ずさみながら、足取り軽く隆矢の後に続く。そしてどきどきと高鳴る胸を押さえつつ、そおっと遠慮がちに室内に足を踏み入れた。
「わぁーーーい」
優里は目をきらきら輝かせて一目散にベッドへ向かい、勢いよく倒れ込んだ。そしてふかふかの毛布にすりすり頬擦りして、ふふ、と嬉しそうに笑う。
小さい頃から布団生活だった優里にとって、隆矢の大きなベッドはずっと憧れの的だったのだ。
「お兄ちゃんの匂いがするよ」
そう言ってうっとりと微笑む優里。隆矢は思わず額を押さえて低く呻く。
―――優里っ、お前って奴はっ
深いイミがないのは分かっている。優里は超が付くハコ入り。激が付くオクテなのだ。隆矢は心なしかよろよろした歩みで近付いて、
「こら、ベッドの上でふざけるな」
「はぁ〜〜い」
優里は甘えた返事を返して起き上がり、ベッドの端に座って室内をぐるりと見回した。
「そんなに面白いか? 俺の部屋」
優里はそれには答えず、ちょっと小首を傾げて切なく笑う。こう言いたかったのだ。だって、大好きな人の部屋だもん。無造作に投げ出してあるシャツとか広げたままの本とか、何もかも全て愛しくて、目に灼き付けておきたいと思うんだよ――――
さっきまでの浮かれた気分が、あっという間にしぼんでしまった。優里は俯いて、膝の上の手をじっと見つめる。
これで良かったのだろうか。隆矢が自分のためにしてくれたことは本当に嬉しいし、感動したけれど、このままではずっと永遠に隆矢のことを諦められなくなってしまう。
隆矢は優しいから、きっと自分のことを厳しく突き放すことはできないだろう。そしてその優しさに甘えて、いつまでも頼って傍にくっついて………
「優里? どうしたんだ?」
楽しそうにはしゃいでいたのが、急にしょぼんと項垂れてしまった。と思ったら、目をこしこしとこすって「もう帰るね…」と涙声で告げる。
隆矢は慌てて引き止めた。これからちゃんと伝えねばならぬことがあるのに。
「ま、待て、優里。マンションまで送ってってやるからもう少し―――」
「いや。これ以上優しくされたら、ぼく、ぼく…………」
苦しそうに肩を震わせる優里に労わりの眼差しを送ると、隆矢はすっと立ち上がった。そしてデスクの陰に隠しておいたものを持って、再び優里の隣へ。
「お前に、やる」
優里は湿った長い睫毛をぱたぱたと撓ませて、隆矢が差し出したものをぼぅっと見つめる。それは余りに身近な、余りに見慣れたもののはずなのに、何故かとても新鮮に見えた。
「お兄ちゃん、これ………」
「ん、ああ……俺が作った……ブーケだ」
「お兄ちゃんが…?」
隆矢の手の中にあるのは、汚れなき雪原を思わせる白いブーケ。白いポンポンマムにグリーンアイスという品種のスプレーバラ。甘い香りを漂わせているのは白スイセン。クジャクヒバの緑が白を引き立たせ、全体を引き締めている。
隆矢は照れ臭いのか優里から僅かに視線を逸らして、
「お前が作ってるのを見よう見まねで覚えてやっただけだから、まるでなってないとは思うけど、でも、お前のことを想って一生懸命作ったんだ。受け取ってくれるか?」
優里はふわふわと頷いて両手でそおっと受け取り、熱い溜め息と共に感嘆を捧げた。
「なんて……すてきなブーケ……。優しくて、温かくて、清らかで………」
白スイセンの上にぽつりと透明の雫が落ち、ころころと転がっていった。まるで、花が泣いているように見える。
しかしもちろん、涙の主は優里。ブーケを潰さないようふわりと抱き締めて、
「僕……こうして花束もらったの初めて………うれしい………」
「だろうな。お前はいつもいつも人のために作るばっかりで、自分がもらうことなんて想像もしていなかったんだろう」
優里は輝く黒瞳で隆矢を見上げ、
「こうして自分がもらって初めて、花を贈るということの素晴らしさを本当に知ることができたよ。お兄ちゃん、ありがとう。ぼく………」
くしゃりと顔を歪めて激しくしゃくり上げつつも、今の気持ちを精一杯の言葉で伝える。
「今日のこと……一生わすれない。この花が……枯れてしまっても、お兄ちゃんがくれたものは………ずっとずっと、僕の中に……ぇっ、ぇぇっ………」
「優里………」
「でも、でも僕……なぁんにも返せないの………こんなにいっぱいもらったのに、僕はお兄ちゃんのために何にもしてあげられない……ごめんね、ごめんねぇ…………」
優里は自分が情けなくて恥ずかしくて、小さく小さくちぢこまってしまう。
お兄ちゃんには幸せになって欲しいなどとかっこいいことを言いながら、心の底では自分から離れていかないでと願っていた。今度はうまくいくといいねと応援しながら、失恋したと聞けばほっと胸を撫で下ろす。それに比べて隆矢の深く真摯な愛情―――
―――これで……十分。もう十分だ………
優里はほぅっと深く息を吐き、もう一度隆矢にお礼を言って帰ろうとした。余り遅くまでいたら迷惑だろう。
するといきなり腰を抱き寄せられ、優里の華奢な身体はそのままの勢いで隆矢の胸の中に倒れ込んだ。
「お…兄ちゃん……?」
ブーケが潰れないようにかばいつつ、目をくるんと見開いたあどけない表情でじっと見上げる。
その愛らしさに、隆矢は一瞬言葉を捨てて行動に移りそうになる。が、何とかこらえて震える舌を駆り立て、彼らしい言葉で想いを告げた。
「なあ、優里………もう、お前のこと好きになっちゃ駄目か?」
優里はぽわんと口を開けて、今の言葉を必死に反芻する。お前が好きだとか愛してるとか、そんな風に言われたらたぶん、すぐに信じることはできなかっただろう。
でも、この告白には隆矢らしい思い遣りが溢れていて、優里は戸惑うことなく込められた真情を汲み取ることができた。
「ぅっ、ぅぇっ、ぇっ、ぇぇっ…………」
優里はブーケをぎゅぅっと握ったまま――――
「ぅ…ぅぁ………ぅあああああああーーーーーーん」
口を大きく開け、涙を振りまいてわんわん泣いた。隆矢は驚いたものの、すぐに理解した。
そうだ、こいつはずっと泣けなかったんだ。俺の前ではいつも無理に笑顔を拵えて、辛くない、苦しくない振りをしていた――――
「優里、泣け。もっと泣け……」
そして全ての涙を出し尽くしたら、天上の花も色褪せるほどのあの微笑みを、願わくば俺だけの微笑みを見せてくれよ――――
「ほら、優里。まだ鼻がくしゅくしゅしてるぞ。もう一回ちゃんとチンして」
「ふゎぁい………」
泣きすぎたせいか半ばぐったりした優里は、隆矢に言われるがまま鼻をチンとかんで、ぐずぐずとすすり上げた。
「よしよし、いい子だいい子だ」
大きくて温かい手のひらに頭を撫でられ、胸の奥からじんわりと甘酸っぱいものが融け出す。それは直接涙腺に刺激を与えるものなのか、再び瞳が潤み出した。
「おお、そんな大量の涙、どこにしまってあったんだ」
笑いながらからかう隆矢にむぅっと膨れて、「もう泣かないもんっ」と強がってみせる。しかしいったん騒ぎ出した涙腺を抑えることはできず、赤みを帯びた目の縁に涙がにじみ始めた。
優里は手でこすろうとしたが、その手を隆矢に掴まれてしまった。と思ったら隆矢の顔が近付いてきて、柔らかな唇が目尻に触れた。
「これからは、お前の涙は全部俺が吸い取ってやる」
優里は嬉しさと恥ずかしさで真っ赤になりつつも、もう一方の目を指差して「こっちにもして…」とおねだり。
隆矢は「しょうがねえなあ」と呆れたように言いながら、でろでろに緩んだ唇を押し当ててちゅ、と吸い上げた。
「やん……くすぐったいよぉ……」
腰をもぞもぞとくねらせて、拗ねたように見上げてくる優里には、男の欲望を芯から揺さぶる控え目な、それでいて濃厚な色気が息づいていた。
その時隆矢は突然理解した。何故これまで、自分の恋愛が全てうまくいかなかったのかを。そう、最初からこうなる運命だったのだ。なのに自分は寄り道ばかりしていた。
そのたびに恋愛の神様か女神様かは分からないけれど、お前の道はそっちじゃないとばかりに、親切に軌道修正してくれたのだろう。
―――もう、道を間違えることはない、絶対に………
隆矢は顔を近付けて、優里の唇を塞いだ。半開きの唇はしっとりとしてふわふわで、微かに震えている。
「ふぅん…」という甘えた吐息に呆気なく蕩かされた隆矢は、そっと舌先を挿し込んで優里の濡れた舌を突付いた、が―――
「ひぁっ、ひゃあああああ〜〜〜〜」
悲鳴を上げて飛び上がり、一目散に駆け出して部屋の隅にちぢこまる優里。隆矢はぽかんとして「優里?」と首を傾げる。
対して優里は涙を浮かべて怨めしげに隆矢を見つめ、
「ふぇぇ………べ、ベロぉ……ベロが入ってきたよぉぉぉ〜〜〜」
隆矢はがっくりと項垂れ、「ベロって、お前……」と力なくこぼす。そしてどっこらしょと立ち上がって、まだ怯えた眼差しを送りつつ震えている優里に近付き、
「悪かった、悪かった。ほら、もうベロ入れねえから」
恐がらせないようにそおっと両手を差し伸べる。優里は涙目のまま頷いて甘えた仕草で手を伸ばすと、隆矢はその身体をふわりと抱き上げて、そのままベッドの端に腰を下ろした。
「お兄ちゃんの膝のうえ……あったかい………」
囁きながら首筋に顔をぴったり寄せて、肌の温もりを交換する。
「お前の身体も……ぽかぽかして柔らかくて、甘い匂いがする………」
この素肌を一刻も早く味わいたいという欲望と、大事に大事に守りたいという慈愛の心情が隆矢の中でせめぎ合う。
「なあ、舌入れないから、もう一回キスしてもいいか?」
優里は頬を染めてこくんと頷くと、目を閉じて唇をちょん、と尖らせて突き出した。
―――やばい……可愛いすぎる………
欲望の占有率がぐんぐん上昇するのを感じながら、ぷっくり膨れた初々しい蕾にゆっくりと唇を押し付けた。
「んん……」
ささやかな吐息と唇の柔らかさに溺れながら、隆矢は情欲との甘く苦い闘争の始まりを予感したのだった―――

駅南口から歩いて3分。昔ながらの人情味溢れる商店街に、ちょっと変わった花屋さんがあります。
大きな酒屋にそっと寄り添って季節の花々を提供するその店は、店舗と呼ぶには余りに小さく、ささやかなスペースですが、商店街の人気者。
特に若く愛らしい店主が心をこめて作るブーケは<幸せを呼ぶ魔法のブーケ>と呼ばれ、好きな人に贈ると必ず想いが伝わるという評判のブーケなのです。
楓町商店街の<フラワーショップ美園>。みなさんもぜひ一度、お越しください。きっと、素敵な笑顔と優しい魔法に出逢えるはずです――――
(Fin)
*最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。
BACK TOP INDEX