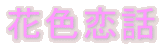
―小さな花屋の物語―
第14話
有栖川と隆矢は、ただ黙って優里の後についていった。
花屋を出てから彼がじっと何かを考えているのは、その表情を見ただけで分かる。きっと、自分なりの答えを出そうとしているのだろう。だからその邪魔をしないよう、彼の歩みをただ後ろから見守るだけにしていた。
駅の中を通らず、高架線の下をくぐって南口に出る。少し歩くと、小さな公園が見えてきた。そう、ホストになると言って出ていった隆矢との、決定的な断絶に涙したあの公園。
あれ以来訪れたことはなかったけれど、優里は真っ直ぐ足を向けて中に入っていった。有栖川も隆矢も、戸惑いつつも後に続く。黄昏色に包まれた小さな公園は人影もなく、ただひっそりと木々が呼吸していた。
「有栖川さん、隆矢お兄ちゃん。僕の話を聞いてくれますか?」
二人はもちろんと言わんばかりに頷く。
「今日は、ありがとうございました。あのお店に連れて行ってもらったお陰で、僕は見失いかけていた自分というものを取り戻すことができました。僕は…あのお店には行きません」
有栖川は少なからずショックを受けたようで、微かに眉根を寄せて「何故?」と訊ねる。優里はそんな有栖川を労わるかのように、優しい微笑みを向ける。
瞳は潤んで一番星のようにちかちか瞬いていたが、それは悲しみの涙ではなかった。もっともっと心の深い部分から湧き上がってくる、温かく崇高な感情の結晶。
有栖川も隆矢も、その澄んだ美しさに心打たれ息を呑む。そして、今さらながらの感慨を反芻した。ああ、彼はこんなに綺麗な人だったのか、と。
そんな二人の思惑を措いて、優里は胸の裡を打ち明ける。淡々と、しかし情熱を込めて。
「あのお店……本当に素晴らしかった。活気があって、明るくて、花たちが生き生きと呼吸しているのが肌に伝わってくる。店長さんも店員さんたちも花が好きで、この仕事に誇りを持っていることも分かりました……」
優里はほぅっと息をついて、言葉を続ける。
「有栖川さんは、あなたが蒔いた種が花開いたのだと言ってくれました。だとしたら、そんな僕を優しく育んでくれたのは、この商店街なんです。楓町商店街という温かな土壌でこそ、僕はのびのびと成長することができた。
だから僕は、やはりここに残ります。そしていつになるか分からないけれど、また楓町で花屋を開きます。あんな立派なお店でなくてもいいの。小さな場所を借りて、そこで自分ができる限りの恩返しをしたい。有栖川さん、それが僕の気持ちです」
「優里さん……」
もっと言葉を尽くして説得すべきなのかもしれない。有栖川は口を開いたが、しかし言葉が出てこなかった。胸が喉がぎゅぅっと圧迫されて、震えているのが分かる。
有栖川は、自分が泣くのをこらえているのだということに気付いた。切なさと苦しさと深い感動に揺さぶられ、自分をうまく制することができない。こんな経験は何年ぶりだろう。
「有栖川さん、僕のために色々考えてくださって、本当にありがとうございます。あのお店で働いたら、きっと楽しいでしょう。
でも、あそこには僕は必要ない。僕がいなくても、あの素敵な店長さんと店員さんたちで素晴らしい花屋を作り上げてゆくに違いありません。だから僕はここでがんばります」
そして優里は、ゆっくりと視線を隆矢に移した。
「それからお兄ちゃん、さっき言ってくれたこと、本当に嬉しかった。お兄ちゃんの言葉はいつも、僕を正しい方向へ導いてくれるんだ」
優里はようやく、自分が泣いていることに気付いた。幼い仕草でこしこしと目をこすり、にこっと笑う。
「覚えてる? 僕はこの公園で、商店街を出て行こうとするお兄ちゃんに行かないでと泣いてすがったよね。あの時は…ごめんなさい。困らせるつもりはなかったのだけど、つい本音が出てしまったの。僕は―――」
優里は、笑顔を保ったまま泣いた。人は、こんなに切なく笑えるのだろうか。こんなに美しく泣けるのだろうか。黄昏と夜の境界で、ひそやかに秘めやかに育まれてきた想いが花開く。
「僕は……お兄ちゃんが好き。もうずっと前から。だから傍にいて欲しかった。どこへも行って欲しくなかった………」
「ゆう…り……」
「ちゃんと伝えるべきだった。でもそうしたらきっと、気持ち悪いって思われて、何もかも全て失ってしまうに違いないと……それが……こわくて………」
やっと言えた。伝えることができた。これで幼馴染みという唯一の繋がりが断たれてしまっても、後悔はしない。これで良かったんだと優里は思った。
「僕はこの楓町商店街で、一生懸命がんばります。だからお兄ちゃんも自分のやりたいことを貫いて。応援してるよ」
呆然と立ち尽くす隆矢に近付き、腕を広げてぎゅっと抱き付いた。
「今までありがとう……」
小さな囁きに溢れる想いを詰め込んで捧げると、すっと腕をほどいて離れた。そして屈託ない笑みを二人に向け、
「それじゃ、僕はこれから病院に行ってきますね」
手を振って、公園から走り去っていった。華奢な背中はあっという間に闇に呑まれ、視界から消えてしまった。美しすぎる笑顔の余韻を残して。
―――僕は、お兄ちゃんが好き……
「嘘だ……だってお前は………」
隆矢は力なく呟いて、優里の消失点を見つめた。華奢な背中は疾うに消え、街灯や車のライトに汚された生まれたての闇があるばかりだというのに。
嘘だ、と呟いたものの、優里の告白が真実であることは疑いようがなかった。と言うより、あれほど真情のこもった告白を、あれほど恭しく捧げられたことなど嘗てなかった。
優里らしい、飾らない真っ直ぐな言葉。そのひとつひとつが心の奥底にまで届いて、隆矢の存在ごと揺さぶった。
それでもその告白に戸惑ってしまうのには、理由があった。だって優里、お前は有栖川のことを―――
「追い掛けなくていいのですか?」
落ち着いた呼びかけに引き戻された隆矢は、ゆっくりと有栖川の方を向いた。
「彼の言葉が信じられませんか?」
「いや……ただ、優里はあんたのことが好きなんだと思ってたから……」
有栖川は「はは、」と乾いた笑いを漏らして、
「だったらいいのですが。僕の方から告白はしたのですが、怯えさせてしまったようで」
「えっ………あんた、優里に何て言ったんだ?」
「あなたを愛してる、そう言いました」
隆矢は思わず額を押さえる。そんな濃厚な言葉を告げられて、優里はさぞ驚き怯えたに違いない。
「それであいつ、寝込んじまったのか………」
「はい。まだ早いと分かってはいたのですが、あなたへの想いを切々と訴えて涙をこぼす彼が余りに愛しくて、つい………」
隆矢は視線を落としてぎゅっと拳を握り締め、
「俺は……これまで何度もあいつにブーケを作ってもらった。惚れた女を手に入れるため、力を貸してくれ、と。そのたびに嫌な顔ひとつせず、一生懸命作ってくれた。お兄ちゃんがんばって、って笑顔で―――」
―――笑顔で? いや、違う……笑ってなかった。あれは、あの顔は……
「笑って…ましたか?」
隆矢の考えを見透かすかのように、有栖川はそっと訊ねる。隆矢は唇を噛んで首を振り、
「いや……笑ってなかった。俺の目が曇ってたから、自分のことしか考えてなかったからちゃんと見えなかったんだ。そう、あいつは泣くまいと必死で笑顔を作って、それで、それで―――」
どれだけ傷付けただろう、辛い思いを強いただろう。それを考えると胸が押し潰されそうになる。
ただの比喩ではない。本当に呼吸ができない、苦しい。隆矢は肩で息をしながら、何でだよ、と呟いた。何でそこまで自分を殺して、俺なんかのために―――
「あなたを愛しているからですよ。当然でしょう? お兄ちゃんには幸せになって欲しい、優里さんの口癖ですよ」
「自分が辛い思いをしても、俺の幸せを願うと? 涙をこらえて、俺が他の女に贈る花束を作ると?」
有栖川は力強く頷いて、清々しい声で答えた。
「だって、それが優里さんではありませんか」
余りにあっさりした分かりやすい答え。そう、真実というのは斯くも単純明快なものなのだ。
「棘で傷付き、冷たい水で荒れてしまった手で、ただ人の幸せを、想いが伝わることを願ってブーケを作る。だからこそ受け取った人の心を揺さぶるのです。魔法の正体、それは優里さんの深く大らかな愛情。それが花に宿ったがゆえに、奇跡が起きるのです。違いますか?」
「……違わない。その通りだ――――」
目を閉じると、懸命に花を選び、試行錯誤しつつアレンジして美しいブーケを拵える優里の横顔が浮かんでくる。
優里はずっと、自分が作ったブーケが<魔法のブーケ>と呼ばれることに戸惑いを感じていた。
僕の力じゃないよ、花の邪気のない美しさと贈る人の気持ちが、受け取った人を幸せにするんだ。そう言って慎ましやかに微笑む。いつも一歩ひいて、ただ人のためだけに―――
「俺は……俺はっ………」
さっき有栖川に投げ付けられた言葉が、閃光のように頭を掠める。
―――君は、優里さんに何をしてあげられる?
何も、何もしてやれない。何もない、空っぽの俺―――
「ちがう……………」
今、隆矢は確信をもって首を振る。してやれることはある。問題は、それを実行するか否かだけ。
「優里、待ってろっ―――」
隆矢は迷うことなく、すごい勢いで駆け出して、公園を出て行った。
「………まったく、僕も馬鹿なことをしたものだ」
あっという間に見えなくなった恋敵の背中に溜め息を送り、有栖川はぽつりと呟く。二人の仲を後押しするようなことをしてしまった。
そんなつもりはなかった。自分はそこまで優しい人間ではない。打算で動き、欲しいものを手に入れるためなら汚い策を弄することも厭わない。
正々堂々勝負する、そんなセピア色の青春物語からは疾うに卒業したはずだった。なのに―――
「やれやれ、なんでこんなに気分がいいんだ」
有栖川は気恥ずかしさを覚えつつも、優里との出逢いによって変わってしまった自分を意識した。後悔はなかった。それに、勝負はこれからなのだ。
「ああ、月が綺麗だなあ……」
有栖川は頭上の皓月を見仰いで、白い息と共にぽつりと呟いた。青臭い青春も悪くはないな、と。
「お父さん、ごめんね。ちょっと遅くなっちゃった」
病室を訪れた優里の顔を見た司は、苦しそうに眉根を寄せた。今日、息子の身に何が起きたかは、質さなくても分かる。
「構わねえよ。つうか、こんな毎日来なくてもいいんだぞ」
「だぁめ。僕が来なかったら、張り切ってリハビリやり過ぎちゃうでしょ? それに、これから暫くはちょっと忙しくなるかも。引越しの準備とかあるし……」
司はじっと優里を見つめて、ひと言「そうか…」と答えた。そして謝罪の言葉を口にしようとしたが、それより先に優里が口を開いた。
「謝らないでね。お父さんが、そこまで僕のことを考えてくれてたなんて……本当に、親の心子知らず、だね」
そう言ってにっこり微笑む優里の顔に、迷いの翳はなかった。司はほっと息をつき、
「有栖川さんが紹介してくれた新しい店、気に入ったか? きっとお前なら―――」
「僕は、あそこには行かないよ」
司は口をぱくぱくと動かした挙句、「なんでだ…」と掠れ声で訊ねるのが精一杯だった。優里は近付いて司の手を取り、
「僕が理想とする素敵なお店でした。だから僕はもっともっと努力して、いつかああいうお店を楓町商店街に開きたい。お父さんと一緒に」
「優里……お前は………」
後の言葉が続かない。司は改めて息子の顔をじっと見つめた。何もかも解っているつもりだった。彼の弱さも強さも。なのに―――
「はは……子の心親知らず、だな。優坊、一緒に楓町に帰って、また花屋をやろう。なぁに、小さいとこで構わねえ。何ならワゴンで移動しながら花を売るって手もある。だからこの身体が動くようになるまで、もう少し待っててくれよ」
「うんっ」
最近は蒼褪めていることが多かった頬を赤く染めて、優里は嬉しそうに頷いた。が、すぐに表情を曇らせて、
「お父さん、どうしたのっ?」
司の両目から溢れる涙を、慌てて拭ってやる。
「ったくなあ。優坊、馬鹿な親父を許してくれよ」
優里はふわりと微笑んで、流れる涙を優しく拭い続けた。
BACK TOP NEXT