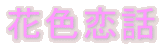
―小さな花屋の物語―
第13話
―――がんばらなくちゃ、がんばらなくちゃ
そう呟くたびに、自分が狭い路地に追い込まれてゆくような不安に襲われる。先は行き止まりで、何の光も見えない。
このまま歩き続けたってどうしようもないと分かってはいるのだけれど、立ち止まることも道を変えてみることもできない。ひたすら前に進むしかないのだ。焦りに駆り立てられるままに。
最近、ミニブーケがよく売れ残るようになった。以前は、出したらほんの一時間で売り切れることもよくあった。なのに今は、手に取って眺めた挙句、買わずに桶へ戻してしまう客が多い。
きっと、最近桜町商店街にオープンしたという花屋の方へ客が流れてしまったのだろう、優里はそう思うことにした。いつだったか、有栖川がぜひ店長にと誘ってくれたお店だ。
確か大手フラワースクールが資本参加しているということだった。綺麗で明るくて華やかで、ブランドショップみたいに洗練された外観のお店なのだろう。気にならないと言えば嘘になるけれど、他店を偵察する余裕など今の優里にはなかった。
「がんばらなくちゃ、がんばらなくちゃ……」
誰かに頼ってばかりだったこれまでの自分をリセットし、一人でもちゃんと生きていけることを証明するのだ。父のサポートがなくても、隆矢が傍にいてくれなくても、自分で何もかもできるということを―――
「ぅっ……ふぇっ…………」
ちょっとでも気を抜くと、泣き出しそうになってしまう。涙の靄を透かして見る花たちは淋しげに色褪せて、本来のみずみずしさを失っている。
こんなことでは美しいブーケを作ることなんてできない、優里は自分を叱咤して乱暴に目をこすり、新しいミニブーケの制作に取り掛かろうとした。その時、店頭から「すみません」という声が。
エプロンの汚れを簡単に払って出ていくと、そこには白髪の好々爺然とした男性が笑顔を浮かべて立っていた。
「こんにちは。私は有栖川さんからご紹介いただきました、藤木不動産の者です。こちらの店舗兼ご住居の明け渡しについての日程を、ご相談させていただきたいと思いまして―――」
「………え?」
優里が思わず聞き返してしまったのも無理あるまい。男性は一瞬、辛そうに目を細めたが、抱えていたファイルから一枚の紙を取り出して優里に差し出し、
「この売買契約書に基づき、店舗と住居を明け渡していただくことになります」
「う、うそ……」
差し出された紙に書かれた細かい文字を読む余裕などなかった。しかし、
「お…父さん……」
左手で必死に書いたのだろう、売主の欄に歪んだ父の名前が記されていた。紙がたわむほどの筆圧に、意志の強さが表れているようにも見える。そして保証人の欄には、有栖川の名前が。
「やっ、やだっ、やだああぁぁ………」
「優里さんっ」
角から有栖川が飛び出してきた。できれば自分は立ち会わずに済ませたかったが、突き付けられた現実にショックを隠しきれずふらふらよろめく優里を、黙って見ているわけにはいかなかった。
今にも倒れそうな優里の身体を抱き留めようと腕を伸ばす。しかし優里はその腕をぱしりと弱々しくはたき、
「どうしてっ、どうしてこんなひどいことするのっ………有栖川さん、信じてたのにっ…………」
怒りと悲しみで盲いてしまったのか、優里はいやいやと首を振りながらどこへともなく逃げ出そうとする。
「優里さん、待って、待ってください」
有栖川は、多少の荒っぽさは止むなしと優里の身体を強引に抱き取り、落ち着かせようと背中をさする。騒ぎを聞き付けた商店街の人間が、徐々に集まり始めていた。
「おいっ、てめえ! 優里に何してやがんだッ」
相太や敦彦など、優里ファンの三代目たちが物騒な声を上げて詰め寄る。しかし有栖川は視線を鋭く尖らせて威嚇し、近寄らせようとしない。もしかしたら、こちらが彼の本性なのかもしれない。
相太も敦彦もその迫力に気圧されて、立ち止まって睨み返すことしかできなかった。
「やだぁぁ……できるっ、僕がんばるもん………」
有栖川の胸をどんどん叩きながら、苦しそうに繰り返す優里。時折激しく咳き込むその背中を撫でながら、
「許してください。こうするしかなかったのです………」
有栖川は何度も何度も許しを乞うた。
「……すみませんでした。あなたに酷いことを言ってしまって。あの不動産屋さんにも嫌な思いを―――」
「気にしないで。優里さんが驚くのも当然です。それに、藤木さんは人の心が解る誠実な方です。全てお任せして大丈夫ですよ」
有栖川の温かい腕の中で徐々に平静を取り戻していった優里は、ひとまず店を閉めて有栖川と共に自宅に戻った。
ちゃぶ台の上の売買契約書をじっと見つめ、
「お父さんが……頼んだのですね。ここを売って欲しい、と」
「はい。あなたには最後まで黙っているように、と。とはいえ、あなたを騙したことには変わりない。申し訳ありませんでした」
優里は視線を契約書に据えたまま、力なく首を振る。
「僕が……もっとしっかりしていたら、お父さんも安心して任せてくれたでしょう。僕がお見舞いに行くたびに、優坊、無理はするな、店よりお前の身体の方が大事なんだと………」
優里は両手で顔を覆って、指の隙間から掠れた謝罪を漏らした。お父さんごめんなさい、お店を守れなくてごめんなさい、と―――
有栖川はそっと近寄り、小さく震える肩をふわりと抱き締める。初めて会ったころに比べて確実に細くなった肩。有栖川の心はきりきりと音をたてて軋んだ。
「優里さん、今度、新しい住居を見に行きましょう。いい物件を紹介してもらったのです。病院に近くて、セキュリティも強固で、バリアフリーで―――」
「有栖川さんが選んでくださった場所でけっこうです。全て、言う通りにします………」
「優里さん……」
「僕は不動産のこととかよく分かりませんし。ここの明け渡しも、全てあちらの予定に合わせます」
投げやりで虚ろな口調。まるで、自分自身を明け渡してしまったかのような。有栖川は一瞬、激しい後悔の念に襲われた。果たして、これで良かったのだろうか、と。
しかしそれを押し殺して「分かりました」と答え、肩を抱く腕に力を込めようとした。その時、
「優里、優里ッ! いるのかっ?」
店先から聞こえる叫び声。やがて僅かに開いていたシャッターをくぐってきたのか、隆矢が姿を現した。
「お兄ちゃん……どうしたの………?」
「こ、この店舗が売りに出されたって今聞いて………本当なのか?」
優里は、身体の中に残っている僅かな意志力を総動員させて笑顔を拵え、
「うん、そうみたい。でも、仕方ないんだよ。僕一人じゃだめなんだ。ほんとは分かってたんだけど、でも、死ぬ気でがんばれば何とかなるかも、って甘い考えを………」
笑顔は長続きしなかった。緩やかな曲線を描いていた唇はわなわなと震え、生気のない無機質な瞳から涙の珠がひとつふたつこぼれ落ちる。
隆矢は拳を握り締めて有栖川を睨み、
「……あんたがやったのかっ?」
険しく淀んだ声で詰め寄る。優里は慌てて隆矢を制し、
「お兄ちゃん待ってっ。有栖川さんは、お父さんに頼まれたことをしただけなの。だから―――」
必死に庇おうとする優里に温かい眼差しを向けた有栖川は、一転、険しい視線で隆矢を見据え、
「確かに、司さんに頼まれました。しかし僕自身も、これが最善の策だったと思っています」
「違うッ」
有栖川の言葉を断ち切る隆矢の叫びには、信念とも呼ぶべき強い想いがこもっていた。それに弾かれて、優里も有栖川もはっと目を瞠る。
「あんたも親父さんも何にも分かっちゃいねえ。この店と楓町商店街は優里のすべてなんだ。確かに危なっかしいところもあっただろう。でも、こいつが納得いくまでやらせてやるべきだったんだ」
「お兄ちゃん……」
「こいつは世間知らずだが、誰かに頼りきりの弱い子供じゃねえ。ちゃんと自分というものを持って、懸命に努力する。その姿に心打たれるからこそ、みんなが手を差し伸べようとするんだ。こいつが弱いから仕方なく助けてるわけじゃない!」
何とか平静を装っていた有栖川の表情が徐々に険しくなってゆく。まるで自分の後悔を見透かすかのような隆矢の指摘に、苛立ちが募る。
「………なるほど、君の意見にも一理あることを認めざるを得ない。しかしそれは無関係な外野の意見に過ぎない。改めて君に問おう。では君は、優里さんに何をしてあげられる?」
「それ…は……」
「答えたまえ。さあ。疲労困憊で倒れそうな身体を叱咤して店に出ている優里さんに、君は一体何をしてあげられるというんだ!!」
隆矢は何も答えられない。ただ項垂れて、からっぽの自分を覗き込むことしかできなかった。有栖川は大きく息を吐き、
「優里さん、大声を出して済みませんでした。びっくりしたでしょう?」
「いえ……あの………はい」
確かに、いつも感情を制して大人の余裕を漂わせながら喋る有栖川の、こんな声を聞くのは初めてだった。しかしそれよりも優里の心を揺さぶっていたのは、隆矢の言葉だった。
ただ、単純に嬉しかった。自分がやろうとしていたこと、求めていたものをちゃんと理解してくれていた人がいる。実現は叶わなかったけれど、もうこれで十分だと思えた。
「ありがとう、お兄ちゃん、有栖川さん。ここまで僕のことを考えてくれて。僕は今のままでは、何の取り柄もない子供です。でも、いつかきっと―――」
「それは違うと、今度は僕が言う番ですね。優里さん、ちょっとこれから僕に付き合ってくれませんか? あなたをお連れしたい場所があるのです。できれば隆矢君も一緒に」
隆矢ははっと顔を上げて、二人の顔を交互に見つめる。
「よろしいですね? では、行きましょう」
妙に確信めいた有栖川の誘いに、優里も隆矢も大人しく従うしかなかった。
駅の方に向かったから、電車に乗るのかなと思った。しかし有栖川は駅構内を突っ切って反対口に出た。ここまで来ればもう、彼がどこへ向かっているのか問わずとも分かる。
桜町商店街―――そこはもはや、優里にとって苦い思い出ばかり詰まった場所になってしまった。有栖川が何を考えているのか不審を覚えたが、隆矢が黙って付いてきていることもあって優里も素直に従った。
「あそこです」
有栖川が指差す先にあるのは、商店街全体に清潔感を与える白い外観のお店。
何を売る店かは今さら問うまでもない。主張しすぎず、それでいて嗅覚に安らぎと心地よさをもたらす花々の薫香。馥りのシンフォニー。
「花屋だ……」
有栖川は恬淡と頷いて、優里を促す。大きな窓から見える店内は杏色の夕陽を受けて明るく、花たちが自然の中でのびのびと呼吸しているかのよう。
花は色ごとに分けて配置され、小さい子供やお年寄りも読めるよう大きな字で花の名前と値段が書いてある。
売られているのは花だけではない。花器や食器、キャンドル、リース。クリスマスの飾りつけも万端で、到る所に大小さまざまなツリーが。
どれも個性的なものばかりで、干したオレンジの輪切りやシナモンがオーナメントとなっているものや、袋入りのクッキーやキャンディのツリーもある。眺めているだけでわくわくして、心が浮き立ってくる。
「さあ、中に入ってみましょう」
有栖川に背中を押されて店内に足を踏み入れた。店員の数は多く、みんな笑顔で客に接している。
アンティーク調の家具の上には水を張った大きなガラス器が置かれ、花がぷかぷか浮かんでいた。きっと、落ちた花を集めて浮かべたのだろう。
「すげえな……」
さっきまで沈んだ表情をしていた隆矢も、子供のように目を輝かせてきょろきょろしている。そう、これが花の力なのだ。
その時、店員の一人がこちらに気付いたのか、「有栖川さーん」と笑顔を振りまきつつ駆け寄ってきた。が、傍にいる優里の顔をじっと見るや否や、きゃあっと嬉しそうな悲鳴を上げて、
「もっ、もしかしてこちらは……美園花店の………」
有栖川は少し得意気に胸を張って頷く。すると彼女は満開の笑顔を咲かせて、
「やったあ。やっぱりこの店に来てくれるのですねっ」
その叫びを聞きつけた店員たちが次々と駆け寄る。
「美園さんだっ」
「有栖川さんの話は嘘じゃなかったんですね」
「一緒に働けるんだぁ。超うれしー」
優里は訳が分からず、それでも彼女たちの笑顔につられてにこっと笑う。対して有栖川は呆れたように彼女らを宥め、
「ほらほら仕事中でしょう。店長に怒られますよ」
「はぁーい。店長、店長っ。美園さんが来てくれたんですよっ」
有栖川のひと声で持ち場に戻ったが、それでも優里のことが気になるのか時折ちらちらと視線を送っては、嬉しそうに笑っている。
「有栖川さん、お久しぶりです」
「こちらこそ。申し訳ありません、突然お邪魔して」
近付いてきたのは、見たところ20代後半の女性。きっちりまとめた髪と薄いメイクが、嫌味でない清潔感を漂わせている。
「優里さん、こちらがここの店長さんです」
有栖川の紹介に合わせて、優里はぴょこんと頭を下げた。傍にいた隆矢もつられて一礼する。店長はふふっと秘密めかした笑いを浮かべて、
「仮の店長です。いずれは美園さんがいらしてくれるのでしょう?」
「え? 僕………」
女性店長は微かに眉根を寄せて、
「お父様のこと、ごく簡単にですが有栖川さんから聞きました。心からお見舞い申し上げます」
「あ、ありがとうございます……」
「今が一番大変な時でしょう。でも…部外者のくせにと思われるのを覚悟の上で言いますが、私は美園さんに花屋の仕事を辞めて欲しくないのです。ですから、落ち着いたらで構いませんから、始めは週に二日程度、この店に来てくれませんか? そしていずれはここの店長として、みんなを引っ張っていって欲しいのです」
驚きの余り言葉を失う優里を思い遣って、有栖川が口を挟む。
「その話はまだ早いですよ。今はお父様のことが絶対優先です。ほら、優里さんも驚いて目をぱちぱちさせてますよ」
店長は申し訳なさそうに肩を竦めて、
「そうですね。ごめんなさい、先走っちゃって。でも、私たちはみんな美園さんを待っているということを、お伝えしたかったのです」
そして、お店を彩る花たちに負けない笑顔で「私たちはみんな美園さんの“子供”なんです」と言い添えると、軽く一礼して仕事に戻っていった。
「こど…も……?」
有栖川は、不思議そうに首をひねる優里の肩を優しく抱き、店内をぐるりと見渡す。
「優里さん、ここの店員は店長も含めてみんな、以前あなたにブーケを作ってもらったことがあるのです」
そして、今まさに花を買っていった幼い子供を指差した。その子の手には、一輪の真っ赤なガーベラが。丁寧にラッピングされて、ふわふわのリボンでおめかしされている。
「ご覧なさい。ここでは、一輪の花を美しくラッピングしてくれる。ブーケを作る際には、贈る相手の好みやシチュエーションを考えて花を選び、リボンやペーパーを吟味する。花の生け方、飾り方が分からないという人には丁寧に応対し、色々なアイデアを伝授してくれる―――」
有栖川の言わんとすることが分かってきた。優里は「ああ……」と深い感慨を漏らし、震える瞳で明るく活気ある店内を見渡した。有栖川は深く頷き、
「そう、あなたの蒔いた種は確実に根付き、芽を出し、見事に花開いたのです。自分は何もできない子供? 何の取り柄もない? とんでもない! 自分を卑下しないで欲しい。それを分かっていただきたくて、今日、ここへお連れしたのです」
優里はそっと目を閉じ、有栖川の言葉を噛み締める。目を開けると、涙のせいか視界は少し曇っていたけれど、明るい光がどこからか射し込んでくるのが分かった。あらゆる迷い、不安を一掃し、確かな道へ導いてくれる清らかな光。
「ありがとう……」
優里は誠真込めてお礼を言い、柔らかく微笑んだ。
BACK TOP NEXT