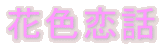
―小さな花屋の物語―
第12話
どちらから言い出したわけでもなかったが、無言のまま歩いて気が付けば小さい頃よく遊んだ川原に来ていた。茶色いものが増え始めた原っぱをさくさく音をたてて踏みしめ、川の近くまで下りる。そして、傾斜が緩やかな場所にすとんと腰を下ろした。
「優里、こっち来いよ」
優里は何も言わず、それでも素直に隣に座る。冷たい風が吹きぬけて、思わずぶるっと身体を震わせた。
「少し寒いか? ほら、これ引っかけてろ」
上着を脱いで肩に掛けてくれる。優里は「要らない」と固辞しようとしたが、上着の内側にこもった温もり、隆矢の匂いが与えてくれる安らぎに逆らえず、すっぽりと上着にくるまれる。
襟を掴んでぎゅっと引き寄せると、まるで隆矢に抱き締められているような甘く苦い錯覚に浸ることができた。
「ここ、懐かしいなあ……」
隆矢の唇から漏れる追憶の囁きは、限りなく優しい。優里も同意したかったが、唇をきゅっと噛んで言葉を閉じ込めた。
思い出の共有は、今の優里には苦しすぎる。ひたすら上着を掴み、間接的な温もりにすがった。
その時、ぴちゃん、と水の跳ねる音がした。優里は顔を上げて、不思議そうに暗い川面を見つめる。隆矢は笑って、
「魚が跳ねたんだな。この川も、魚が棲めるまで綺麗になったんだ。俺たちがガキの頃は、ヘドロだらけだったのに」
「うん……」
「自然破壊だ環境汚染だって言われてるけど、こういう事実を目の当たりにすると、人間もまだまだ捨てたもんじゃねえなって思えるよ」
優里は思い出した。隆矢は学生の頃、商店街の清掃活動や川原のゴミ拾いに、率先して参加していたのだ。
そう、隆矢は昔からこの町を、商店街を愛していた。なのにいつからだろう、何とかしてここから出ようともがき始めたのは―――
「あ……優里、ごめん。お前がこんな大変な時に、暢気なこと言っちまって」
「う、ううん……なんか、お兄ちゃんとこういうこと話すの久しぶりだなあって……」
「そうか……。そうかもな………」
隆矢はふうと大きく息を吐いて、優里の方に正面から向き直り、
「美咲と……有栖川さんから聞いた。親父さんの看病と店を両立させるつもりだって」
「うん、そうだよ……」
「優里、よく考えるんだ。両方は無理だ。お前のことだから、どちらか手を抜いて要領よくやるなんてできないだろう。どっちも完璧に、全力でやり遂げようとするはずだ」
優里は上着の襟に鼻をうずめ、黙って耳を傾ける。隆矢はさらに近付いて優里との距離を縮め、
「今だってもう、相当辛いんだろう? もともと小さくて細っこいのに、こんなにやつれちまって……。優里、無茶はするな。今は店を閉めて、そして―――」
「いや……できるもん、がんばれるもん………」
隆矢は手を伸ばして優里の頬を手のひらでふわりと包み、自分の方を向かせた。
「親父さんが治ったら、また二人で店をやりたい。だからそれまでがんばる……その気持ちは解るよ、けどな―――」
「違う」
隆矢の優しい宥めを容赦なく断ち切る勢いで、優里は鋭い否定の言葉を投げ付ける。隆矢ははっと息を止めて、優里の瞳を上から覗き込んだ。
真摯な輝き、魅惑の揺蕩い。暗闇の中でもその黒い輝きを誇示する双つの宝石に、隆矢は魅入られ、酔わされ、吸い込まれそうになる。
「お兄ちゃん……有栖川さんから聞いたんだね。そう、僕は確かにそう言った。でも、僕は有栖川さんに嘘をついた」
「嘘……?」
「うん。またお父さんと二人で店をやりたい、それは嘘じゃない。でも、僕がこうやって意地を張ってお店を続けている理由は違う。僕は、僕にはこれしかないから、だから……」
美しい瞳が、苦悩と悲しみに犯されてゆくのが分かる。輝きの代わりに涙が次々と溢れる。
「僕からこの仕事とお店を取ったら何が残る? なんにも、なぁんにも残らないよ。何の取り柄もない、心も身体も弱いただの子供。そうでしょう?」
身を乗り出して、痛々しいほどの真剣さで問いを差し出す。僕という人間に、どんな価値があるの?と。その問いの重みと切実さに圧倒され、隆矢は言葉を返すことができない。
「僕がお店のために頑張ってるんじゃない。僕がお店に、花屋という仕事に支えてもらってるの。柾矢お兄ちゃんも隆矢お兄ちゃんもいなくなって、一人になった僕の唯一の……明るい光………だからもう………」
優里は手を伸ばし、隆矢の胸に爪を立てた。そして涙にむせながら懇願する。
「もうこれ以上、僕から奪わないで、お願い………」
震える肩をその涙ごと、訴えごと抱き締めてやる以外に、隆矢に何ができただろうか。
「やあ、恥ずかしいな。こんなみっともねえ姿晒しちまって」
ベッドの上で、照れ臭そうに笑う司。有栖川は椅子を引き寄せて座り、
「何を仰るのですか。お医者さまに聞きましたよ。普通なら30分でへばってしまうリハビリを、2時間も続けたとか。みっともないどころか、不屈の鉄人です。恐れ入ります」
そして和やかな空気の中、他愛もない世間話に花を咲かせる。しかしそうしながらも、有栖川は優里のことを切り出すタイミングを計っていた。
隆矢が説得したはずだったのに、優里は未だに店をやめる気配も見せず黙々と働いていた。
疲労が蓄積しているのか、表情豊かなはずの顔は鉛色の翳に覆われて無表情に沈み、好奇心旺盛な小動物のようにくるくる動く瞳は、重い倦怠を背負って淀んでいた。
このままでは、責任感と疲労の重圧に耐え切れずぺしゃんこに潰れてしまう。それを黙って見ているわけにはいかない。自分や隆矢の説得が聞き入れられないのなら、もう司本人に諭してもらうしかなかろう。
しかし、それを司に頼むのはさすがに心が痛む。彼だって店が大事なはずだし、早く治して仕事に復帰したいという強い思いが、苦しいリハビリに向かう原動力になっているのだろうから。
「優里さんは……今もお店なんですね」
「ん? ああ。そうみたいだな」
有栖川は呼吸を整えて、そして身を乗り出した。お父さん、お願いがあるのです、優里さんを―――
「有栖川さん、あんたに頼みたいことがあるんだ」
有栖川の思惑を見透かしたかのように、僅かに先んじて司が口を開いた。有栖川ははっと息を呑んで固まり、やがて掠れ声で「なんでしょうか…」と訊ねた。
司は麻痺のない左手を伸ばしてサイドテーブルの引き出しを開け、中から家と店の鍵を取り出した。戸惑う有栖川にそれを渡し、そして頼みごとを口にした。それを聞いた有栖川はこくりと喉を鳴らし、
「本当に……よろしいのですか?」
「ああ。考え抜いた結果だ。考える時間だけはたっぷりあったからな」
「優里さんには……」
「済まねえが全て終えるまで黙っててくれ。あいつは俺に似て案外頑固だからな。何がなんでも阻止しようとするだろう。優里にはショックだろうが、こうするしか方法はねえんだ。有栖川さんよ、後のフォローは頼んだぜ」
そう言って笑う司の顔は、子供の幸せと健康を何よりも願う親の顔だった。迷いも未練もない、清々しい笑顔。
恐らく彼はこの2週間、悩み、苦しみ、幾度も自問自答を繰り返しただろう。そして自ら出した結論を、誇りを持って遂行しようとしている。
司の愛情深さ、それに基づく決断力に、有栖川は深い敬意を抱かずにはいられなかった。
「あんたにも色々心配かけちまったな」
司はそう言って、労わりの眼差しを送った。彼がここまで優里のことを想っていると気付くことすらできなかったと、有栖川は自分の考えの浅薄さを噛み締めつつそっと首を振った。
「それじゃ、僕はそろそろお店に戻るね」
「そうか。優坊、あんまり無理すんじゃねえぞ」
優里は力ない苦笑を浮かべて、
「その台詞、そのままお父さんにお返しします。リハビリがんばるのもいいけど、先生の言うことちゃんと聞くんだよ」
そして洗濯物の詰まった紙袋を提げ、部屋から出ていった。ひと回りもふた回りも縮んだ息子の背中を目に灼き付け、自分の判断は間違っていないと言い聞かせる。
司にもまだ迷いはあった。果たして、あれで良かったのかと。優里のためになる選択だったのかと。
「もう……遅えか………」
今さらうじうじ悩んでもどうにもならない。有栖川に託してしまったのだから。そう、賽は投げられたのだ――――
「……おやじさん」
目を閉じてさまざまな思いを巡らせていた司は、ためらいがちに呼びかけられてふっと目を開けた。そしてゆっくり顔を横にずらすと、まるで親からの叱責を待つかのような面持ちで、隆矢がぽつんと立っていた。
「おお、隆矢か。よく来てくれたな。そんなとこ突っ立ってねえでこっち来い」
何しに来たんだ帰れ、そんな言葉を予想していた隆矢はほっとした様子でこくんと頷くと、ベッドの傍に近付いて上からじっと見下ろした。
「珍しそうな目で見るんじゃねえよ。ほら、その椅子に座れ」
隆矢は長身を折り曲げてのろのろと椅子に腰を落とす。と思ったらいきなり拳を膝に叩き付けて、
「なんでっ……なんでだよ、親父さんまでっ………」
あとの言葉は涙と嗚咽に掻き消され、喉の奥で消えた。隆矢は項垂れたまま、暫く肩を上下させて泣いていた。ぽつぽつと涙の雫が降りかかり、ジーンズに小さな水玉模様を描く。隆矢は忌々しげにその痕跡を指でこすり、
「あいつが………可哀想だっ…………」
司はふんと鼻で笑い、
「大丈夫だ、心配は要らねえ。優里には有栖川さんがいるからな」
新たな涙の跡をこすろうとした手が、ぴたりと止まる。そのまま厚手の生地にがりがりと爪を立て、
「俺は……どうしようもないガキだ、とんでもないバカだっ………失ってしまってからようやく、それがどれほど大事なものだったか気付くなんて―――」
何のことだ、とはもちろん訊かなかった。ただ司は親愛を込めて、「ああ、お前はどうしようもないバカだ」と応じる。隆矢は天井を仰いで涙を拭い、
「ったく、少しは否定してくれよ………これでも相当ショック受けてんだぜ………」
「バカだからバカだっつってんだよ。もう失っちまったと決め付けてるところなんか特にな。本当に救いようのないバカだ。金魚すくいの水槽で泳ぐ鯉みたいなもんだ」
隆矢はがっくり肩を落とし、
「すくいようがない、って? なんだよそれ、笑いどころかよ。笑えねえっつうの」
司は「しょうがねえなあ」と笑い、暫し項垂れた隆矢の前頭部を眺めていた。が、声を厳しく引き締めて、
「おい、隆矢。おめえ、何で徹っちゃんに言わねえんだ。自分の本心を」
「なんの……本心だよ………」
「阿呆か。お前の本心だっつってるだろ。店を継ぎたいという気持ちだよ」
いきなり核心を衝く言葉を投げられて、隆矢はかわすことも打ち返すこともできず、その衝撃をまともに喰らった。
「お、俺はっ―――」
「お前、柾矢と二人で店を継ぐつもりだったんだろ? 兄弟二人で沢村酒店を、楓町商店街を盛り立てていこうって。なのに、柾矢からお前は好きなことやれ、店は自分が引き受けるからって言われて、突き放されたみたいに感じたんだ」
瞬きせず呆然と見返すばかりの隆矢を温かく労わるように見つめ、司はぽつりと加えた。
「お前はいらない、自分ひとりで十分だ、ってな」
もやもやと溜め込んできた想いが、今、司の手によって全て引き出された。隆矢は潔く認めた。ああ、そうだ。俺はずっと、店を継ぎたいと思っていたんだ、柾矢と二人で………
「戸惑っただろ? 驚いただろ? お前は好きなことやっていいって言われて。ずっと店を継ぐつもりだったお前さんは、仕方なく別の道を探し始めた。でも今さら、どうしていいか分からねえ。そうやってもがいている途中で、柾矢が事故で死んじまった。
すると今度は、全てがお前の肩にのしかかってきた。そう、柾矢の代わりに店を継がなくちゃならなくなったんだ………」
隆矢はもう呆けてはいなかった。表情を引き締めて頷き、
「親父さんの言う通りだよ。俺は柾矢と“一緒に”店をやりたかった。柾矢の“代わり”になんて考えたこともねえし、無理だと分かっていたから。だから恐くて逃げ回って……」
「だからお前はバカだっつうんだ。何で無理なんだよ。誰が決めた、そんなこと」
隆矢は腰を浮かせて、「だってそうだろう!」と大声で詰め寄る。
「どうして柾矢が、なんで柾矢がこんな目に、って………なんで、隆矢じゃなく柾矢なんだ、って……みんな、みんなそうだ………親父もお袋も、商店街の仲間も………優里も…………」
司は大きな溜め息をついた。喋るのは体力を消耗する。疲労で全身がだるくなってきたが、ここでやめるわけにはいかない。呼吸を整えて再び口を開こうとした時、隆矢がぽつりとこぼした。
「俺には……何の取り柄もない……ただの………」
その時、隆矢の頭で何かがちか、と瞬いた。同じ台詞を、いつかどこかで聞いた記憶がある。そうだ、あれは………
―――何の取り柄もない、心も身体も弱いただの子供。そうでしょう?
「優里……」
そうだ、優里もきっと、こういう気持ちなのだ。今なら分かる。痛いほど分かる。誰にも必要とされない無価値な自分と向き合い、それを何とか克服したいと―――
「なあ隆矢、お前さんは大きな思い違いをしている。柾矢はお前を突き放したんじゃねえ。あいつはずっと、お前に負い目を感じていたんだ」
「負い…目……?」
「おう。柾矢はガキの頃、病気がちだったよな。そのせいで、親は自分にばかりかかりきりで、甘えたい盛りのお前は一人でいることが多かった。だから今度は自分ががんばって、お前には好きなことをして、自由に楽しく生きてもらいたい、と」
隆矢は黙って頷いた。そうだ、その通りだ。サッカー部の合宿から帰ってきた時も、新歓コンパで酔っ払って帰ってきた時も、柾矢はいつも店番をしていた。そして嬉しそうに笑って「隆矢、楽しかったか?」と訊いてきた。
お前は好きなことをしろ―――何故それを愛情と捉えることができなかったのだろう………
「なあ隆矢、お前はお前のやり方でいいじゃねえか。確かに柾矢は人望もあって堅実で、みんなを引っ張っていくタイプだ。
でもお前には天性の明るさ、人とすぐに打ち解けられる柔軟さがある。みんなを引っ張っていくんじゃねえ、みんなと共に協力し合いながら楓町を盛り立てていけばいい。俺はそう思うぞ」
「親父さん、俺………」
何と答えてよいか分からない。けれど、足下が不安定な暗闇の道行きに、僅かな光が見え始めたことは間違いなかった。
司は目を閉じてふぅと息を吐き、
「今すぐ答えを出そうと焦ることはねえけどな。まあ、考えてみてくれ。悪ぃな、隆矢。たくさん喋ったんでちと疲れちまった。暫く休ませてくれ」
そう言われてようやく、司の顔色が余り思わしくないことに気付いた。自分の未熟さ幼さが、ずんと胸に響く。
「ごめんよ、親父さん。無理させちまって。また…来てもいいかな?」
「………いいとも」
隆矢は思わず吹き出して、立ち上がった。そして乱れた布団の裾を直してやる。
「余計なことすんな。可愛い看護婦さんにやってもらうんだから」
「分かったよ。看護婦さんに手ぇ出すんじゃねえぞ、おやじさん」
来た時に比べると、かなり心が軽くなっていた。追い返されるの覚悟で訪れて、本当に良かったと思う。
「じゃあな」
「おう」
短い挨拶を交わして、隆矢は帰っていった。
BACK TOP NEXT