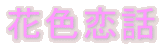
―小さな花屋の物語―
第11話
「……そうですか、半身の麻痺は残るだろう、と」
「はい……でもリハビリ次第では、これまで通りの生活に戻れるようになる、って」
入院手続を済ませ、必要な物を買い揃え、主治医の説明を聞き終えた優里は、ひとまず家に戻ってきた。するとちょうどいいタイミングで有栖川から電話があり、夕食の誘いを受けて駅前の寿司屋を訪れたのだった。
「言語や記憶を司る部分の損傷がなかったのは、不幸中の幸いでした。ただ、利き手の右手が麻痺しているのが……」
優里は俯いて、箸を持った自分の右手を見つめる。父がもう一度、こうして箸を握れるようになる日は来るのだろうか―――
「優里さん、周りにいる人間が悲観的になっては駄目です。最も不安で恐くて絶望しそうになるのは、恐らく本人です。そんな時こそ、あなたが笑顔で肩を叩いてあげねばならない。辛いとは思いますが、できますか?」
優里は下唇を噛み締めて嗚咽を押し込め、力強く頷いた。有栖川はふわりと笑って頭を撫でる。
「リハビリはいつから始めるのですか?」
「できるだけ早い方がいいそうです。筋肉や関節が固まってしまうと厄介なので。最初は簡単なマッサージから。その後は鍼灸治療や加圧マッサージ、鏡を使ったリハビリなど、その人に合ったものを探しつつ進めていくという感じです」
有栖川は「なるほど」と返して僅かに身を乗り出し、
「それで、お店はどうするのですか?」
「もちろん続けます」
躊躇も見せず即答を返す優里。そして、有栖川の懸念や否定的な言葉を先に封じてしまえと言わんばかりの勢いで言葉を続ける。
「市場へは、相太おにいちゃん、さっき病院に駆け付けてくれた人です、それともう一人健ちゃんが交代で運転してくれます。落ち着いたら僕も免許を取るつもりですが。バイトさんは増やせないので、配達は止めて開店時間も縮小することになりますが―――」
「優里さん、落ち着いてよく考えて。それはあなたには無理です」
しかし優里は、彼にしては珍しい鋭い視線を向けて、
「何故決め付けるのですか? もちろんお父さんのリハビリを疎かにはしません。開店準備を終えたら病院へ行き、そしてお昼すぎにお店に戻る。閉店は3時か4時くらいを考えています。
夕方の人出が増える時間帯に閉めるのは忍びないのですが、仕方ありません。それからまた病院に戻れば―――」
優里ははたと口を噤んだ。有栖川が痛ましさを隠そうともせず、自分を見つめているのに気付いたからだ。優里はぎゅっと拳を握り締め、さらに強張った声で、
「絶対にやめません。そしていつになるか分からないけれど、またお父さんと二人で、二人でお店をっ―――」
そこから先は言葉にならない。もし、有栖川がさらに諭そうとしてきたら席を立って帰るつもりだった。しかし有栖川は何も言わず、膝の上で震える優里の左手を力を込めて握った。温かくて大きな手。
一人でがんばるんだと気を張っている優里にとって、その温もりは甘い毒以外の何ものでもなかった。
その翌日から、優里の生活は一変した。朝から市場での慣れないセリに参加し、店に戻って開店準備。入荷品の水揚げや手入れについてバイトに指示を出してから、病院へ。
司の身の回りの世話、リハビリの付き添いをしていったん店に戻り、接客やミニブーケ作りに専念する。そして早めにレジ閉めをして、掃除や閉店業務はバイトに任せ再び病院へ。
午後のリハビリに付き合った後、汚れ物を持って家に帰り、売上計算をしつつ洗濯をして夜のうちに干す。一日を終えた優里はへとへとで、服を着たまま布団に倒れ込むこともあった。
こういう時こそ互助会の出番だと、商店街の面々も協力を申し出てはくれたが、自分の店を疎かにすることはできない。協力にも限界はある。
それに駅前の大型スーパーや華々しく再生した桜町商店街の煽りを受け、徐々に楓町全体の売上が落ちていた。みんな、自分のところの売上を維持するので頭がいっぱいというのも、偽らざる本音だったのだ。
優里は決して泣き言を漏らさなかった。たまに有栖川が様子を見に来てくれた時も、軽い会釈を返すのみ。
あの温かい手に縋りたいとよろめく弱さが、自分の中に確実に存在することを自覚してしまった以上、敢えて避けるしかなかったのだ。
けれど、気力だけではどうにもならぬこともある。優里の身体も神経も、限界を迎えつつあった。
商店街の人間も有栖川もそれに気付いていたが、頑なに意志を貫こうとする優里をどうすることもできず、ハラハラしながら見守っているしかなかったのだ。しかし―――
「すいません、店長。あの―――」
「店長じゃねえっ。オーナーと呼べと言ってるだろがっ」
男は舌打ちしたい欲求を抑えて「すいません」と頭を下げ、そして若いオーナーにそっと耳打ちした。
「今、外に、隆矢に会わせろって女が来てるんですが」
「あん? 客じゃねえのか」
「客という感じじゃありませんね。まあ、恋人でもなさそうですが」
オーナーはバカにしたように鼻先で笑い、
「はん、どうせ初回サービス料金で来て、隆矢に惚れちまったとかそういうやつだろ。二度三度と通う金がねえから、外で喚いてんのか」
そして「さっさと追い返せよ」と顎をしゃくる。しかし男は卑屈に笑って、
「できればそうしてるんすけどね。会わせてくれるまでここから離れないって。他の客の迷惑にもなるし、みっともねえし。エントランスの奴らも困ってますよ。ちょっと会わせてやれば気が済むんじゃないんすか」
「阿呆か。あの状態で隆矢を呼び出せるかよ」
オーナーがそう言うのもある意味尤もだった。客に固く腕を組まれた隆矢は、多少引きつってはいるものの笑顔を浮かべて接客している。
「うわ、ゆかりさんかあ。あのヒト独占欲超強いからなあ」
「だろ? これで呼び出したりしたら修羅場だぜ。分かった。俺が行く」
オーナー自ら階段を上がってエントランスに出る。
「あんたか。隆矢に会わせろっていうのは」
「ええ、私です。で、そういうあんたは誰?」
黒服の男3人に囲まれても美咲は臆することなく、堂々と見返す。
「俺はここのオーナー。で、隆矢に会ってどうすんの」
「伝えたいことがあるの。とても大事なこと。時間はとらせないわ」
男たちは顔を見合わせて肩を竦め、
「あのね、隆矢は今お仕事中。だから、伝言なら俺がちゃんと伝えておくから」
「他人に伝言頼めるようなことは、大事なことって言わないの。今仕事中だっていうなら、隆矢の新しい携帯番号教えて」
「そういう個人情報は勝手に教えられないんだ。知りたいならお店に通って、直接本人から聞き出したら?」
そんな金はないだろ?とでも言いたげな態度に、美咲の怒りはいきなり沸点を超えた。「分かった、そうする」と短く言い棄てて、店の中に無理やり入ろうとする。男たちは慌ててその肩を掴み、
「ちょぉっと待って。君さあ、お金持ってる?」
「うるさいわねっ。持ってるわよ。ていうか離してよ!」
喚きつつも路上に引き出された美咲は、大声で叫んでやろうと大きく息を吸った。その時、
「離してあげなさい。女性にそんな乱暴をして、ホスト失格だよ」
「ああ?」
胡散臭げに顔を上げたオーナーは、途端に顔付きを変えた。
「わっ、有栖川さんっ。どーも、お久しぶりっす」
下っ端のホストは分からないらしく、突然態度を変えたオーナーをきょとんと見つめるばかり。有栖川は見る者によっては凄みを感じさせる笑顔を浮かべて近寄り、声を掛ける。
「美咲さん、大丈夫ですか?」
オーナーは蒼褪めて、
「うわっ、有栖川さんのお知り合いだったんですか。すみません、失礼なことを……」
二人の関係が何となく分かり始めた美咲だったが、ここで急に大きな態度に出るのは権力を笠に着るみたいで嫌だった。だから敢えて穏やかな口調で、
「別に構わないわ。それより隆矢を呼んできて下さい。お願いします」
そして頭を下げる。有栖川も続いて軽く会釈し、
「僕も隆矢君にお話したいことがあります。仕事中申し訳ありませんが、お願いできますか?」
「ええ、そりゃもちろんです。立ち話もなんでしょうから、どうぞ店内へ。すぐ呼んできます」
「いえ、ここでけっこうですよ」
オーナーは「分かりました」と言って階段を駆け下り、あの厄介そうな客とどう話を付けてきたのか、隆矢を連れて戻ってきた。
「美咲っ? どうしたんだお前……それに、あんた………」
隆矢は目を丸くして驚きを露わにしつつ、二人のもとへ。有栖川は目を細めて「久しぶりですね」と答え、近付こうとした。
すると美咲が飛び出して腕をしならせ、鈍く重い音と共に隆矢の横面を張った。
「…………」
痛いとか何すんだとか、そんな言葉も出てこない。隆矢は驚きの余り無反応で、怒りと苛立ちに沸く美咲の顔をぼぅっと見下ろした。
「あんた、いい加減にしなさいよ。いつまでこんなことやってんのよっ」
「何が―――」
「優里がっ、優里が今どんな状況だか知ってんのっ?」
呆けていた表情が一気に引き締まる。隆矢は身を乗り出して「優里がどうしたんだ」と詰め寄る。
「司お父っつぁんが倒れたのよ。脳梗塞で、半身麻痺で……。なのにあの子、お店もやめないって必死で………」
美咲は涙で喉を詰まらせ、激しく咳き込む。ちゃんと状況を説明しなければならない時なのに、涙に翻弄されてしまう自分が腹立たしかった。
すると有栖川が背中をさすりつつ、言葉を継ぐ。
「お父さんの看病やリハビリの付き添いとお店、両立は無理だと諭したのですが、倒れるまで頑張るのだと言って聞き入れてくれません。今は気力で持ちこたえているのでしょうが、このままでは……」
「ほんとに、弱いくせして頑固なんだからっ」
美咲の捨て台詞に同意するように頷いて、
「いつかきっと、またお父さんと二人でお店をやるのだと。だから決してやめないと言っています。恐らく罪悪感もあるのでしょう。ずっとお父さんに頼りきりで、発作の予兆を察してあげることもできなかったと」
「優里……」
考えてもいなかった事態に、隆矢は呆然と名前を呟くことしかできない。
「ですからお願いです。優里さんを説得してください。暫くお店は閉めて、自分の体調のことも考えるように、と―――」
隆矢は有栖川の言葉を聞き終える前に、凄い勢いで駆け出した。そしてあっという間に見えなくなった。
当然だが、店のシャッターはきっちり閉まっていた。隆矢は裏口に回り、呼び鈴を押す。すると程なくして、内側から扉が開けられた。
「お兄ちゃん………」
中から現れた優里は、想像以上にやつれていた。ふっくら優しい丸みを帯びていた頬は削げ、顔がひと回り縮んだように見える。
その分瞳が占める割合が増えたのか、目だけがやけに大きく縋るように見上げてくる。まるで捨てられた仔猫のようだった。
この前会ったのはいつだったろう。そんな前のことではないはずだ。なのにこの痛ましいほどの変貌。目の前の現実に打ちのめされた隆矢は、つい責めるような言葉を吐いてしまった。
「お前……なんで俺に連絡しなかったんだ。司のおじさんがこんな大変なことになってるのに」
優里の瞳は一瞬透き通ったと思ったら、すぐに険しい輝きを帯び始めた。
「どこに連絡すればいいの? 僕、お兄ちゃんの新しい携帯番号知らないもん。今どこに住んでるかも知らないもんっ。またお店に行って怒られるのやだもんッ!」
「優里―――」
「僕ひとりで頑張れるっ。お兄ちゃんなんかいなくたって、ちゃんと、ちゃんとできるんだからぁ………ばかぁ………」
扉を閉めようとする優里を慌てて引き止め、腕の中に抱き止める。微かな抵抗を見せていた優里も、すぐに大人しくなって隆矢の胸に顔をうずめた。
「外、気持ちいいからちょっと散歩しよう……」
優里の同意を待たず、背中に腕を回してそのまま歩き出した。
BACK TOP NEXT