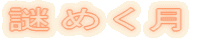
2.
地上48階のダイニングバー。予め話が通っていたのか、カウンターではなく奥の個室に通された時、透麻の疑念は確信に変わった。
さっきの余りにタイミングの良すぎる神谷女史への呼び出しは、彼女、ゆづきが仕組んだことに違いない。恐らく、作品を取りに行くと言って部屋を出た時に、色々根回ししたのだろう。
「透麻さんってお酒強いのね。かなり飲んでいるのに全然変わらないのだもの」
いつの間にか呼称が“先生”から“透麻さん”に変わっていた。透麻は不機嫌を隠そうともせず、黙って水割りに口を付ける。
言葉を交わすのも億劫だったが、このままここで酒を飲み続けているわけにもいくまい。今ごろ、游月が時計とにらめっこしつつ帰りを待ってくれているに違いない。
「そろそろ作品を見せていただいてもよろしいでしょうか」
「ええ」
彼女は素直に頷くと、透麻の前に絵を広げて雄弁に語り始めた。自分がどれだけ透麻の世界に耽溺しているか。透麻の芸術を理解しているか。そうしながらつまりは自分を売り込んでいるに過ぎないのだが。
透麻はそっと溜め息をついた。やはり“どこかで見たことのある絵”の域を出ていない。これなら游月が描いた絵、涙をこぼす三日月の方がずっとずっと美しい。
透麻は頭を巡らせて、断りの言葉を探した。余り厳しいことを言って彼女の機嫌とプライドを損ねたら、面倒なことになりかねない。
「この絵には、それ自体で強烈なイメージ喚起力があります。ですから私の言葉たちが負けてしまう可能性も大いにあり得る。いえ、正直申しまして勝つ自信がありません。ですから―――」
「それなら描き直します。透麻さんが気に入ってくれるものに」
「貴女は―――」
「いや。ゆづき、って呼んで」
透麻の方にぐっと胸を突き出して、膝の上に手を置く。そして潤んだ目でじっと見上げ、
「私、ずっとずっと前から先生の大ファンでした。先生の世界に溺れてる、って言ってもいいくらい。どんな人なのか気になってはいたけれど、最初は勝手に妄想しているだけで十分だった。でも………」
まるで誘うように大きく瞬きをして、ちらと唇を舐める。彼女の身体が放つ動物性のきつい香料とたちこめる酒気のせいか、透麻の頭はだんだん重くなっていった。それとは対照的に、彼女の瞳は不穏なほどきらきら輝き始めた。
「でも『月に游ぐ』を読んで、あの献辞を目にした時私は思ったのです。私と先生は出逢うべきなのだ。そして私の絵こそが先生の世界を支え、より豊かなものにすることができる、と―――」
透麻は黙って彼女の身体を押し戻した。そして、煮詰めたタール状の闇がざわざわと蠕動するかのような昏く剣呑な声で、
「申し訳ありませんが、私はやはり自分の直感を信じます。貴女の絵と私の文章は寄り添うことはできない」
すると夢見る少女のようにうっとりと宙を彷徨っていた瞳が、みるみるうちに硬く強張っていった。
「どうしてっ? 私がここまで言っているのに。他の作家はみんな、私と仕事したがるのよっ」
「他の人なんて知りません。私は、貴女の世界に共鳴できなかった。それだけです」
透麻は静かに言い置くと、立ち上がろうとした。が、
「ま、待って、行かないで。い、いいの? あの若い編集者の将来が潰されても……」
透麻の腕にすがり付いて、胸に顔を押し付ける。しかし、
「どうぞお好きなように。本当に才能のある人なら、一度潰されても必ず蘇ります。私も協力を惜しみませんし」
肩を掴んで強引に引き剥がし、この重く淀んだ空間を後にした。
呼び鈴を押そうかと思ったが、少し考えてやめた。もしかしたら、游月はもう寝ているかもしれない。
ポケットから鍵を取り出して扉を開け、そおっと音をたてずに閉める。そしてやはり足音を忍ばせてリビングへ向かうと―――
「ああ……游月………」
ソファの上で、游月が丸くなって眠っていた。透麻のシャツをぎゅっと抱き締めて。その前にひざまずいて、そおっと寝顔を覗き込む。
いつもの安らかで満ち足りた表情とは違って、眉間に微かな皺を寄せた不安げな顔つき。まるで透麻の匂いに縋るかのように、シャツの中に鼻をうずめている。
「淋しい思いをさせてしまったようですね……」
離れていた時間の埋め合わせをするように、額に、まぶたに、頬に口付けを落とす。游月はうにうにと意味不明な寝言をこぼして、シャツに頬をこすり付けた。
「シャツに嫉妬してしまいそうです……」
透麻は冗談とも本音ともつかぬ呟きを漏らして、游月の手から少し強引にシャツを抜き取り、背中に腕を回してゆっくり抱き上げた。
「んん………と…ま…さん………?」
「はい。游月、遅くなってしまって申し訳ありませんでした。それに、お土産もなくて……」
寝起きの身体はぽかぽかして、いつも以上に柔らかく蕩けるようで、透麻は我を忘れてきつく抱き締めた。游月も嬉しそうに口許を綻ばせて、透麻の胸に顔をすり寄せようとした。しかし、
「い…やッ……」
尖った拒絶の言葉と共に、胸を突き飛ばされる。透麻は訳が分からず、きょとんと目を見開いて游月を見つめた。
「ど…して………透麻さん………」
游月の双眸がじんわり潤み始めるのを、透麻はぼぉっと眺めるしかできない。やがて、
「透麻さんのばかぁっ」
游月はシャツを投げ付けると、呆然とする透麻を残して部屋を飛び出した。そして寝室へ駆け込むと、ばたん、と荒い音をたてて扉を閉めてしまった。
「ゆ…づき……?」
透麻はどうしてよいか分からぬまま、ともかく游月の許へ急ごうと立ち上がって上着を脱いだ。すると、濃厚な動物性の香りがふわっとたちのぼって鼻孔を刺激した。
「こ、これですね………」
透麻はあたふたとシャツを脱いで、新しいものに着替えた。脱いだシャツを無造作に丸めようとした時、襟元に紅く灯る口紅の跡に気付いた。
普段の透麻からは考えられない険しい舌打ちをして、苛立ちを込めてシャツを投げ捨てる。そして游月の許へ急ごうとしたが、自分の首筋辺りから同じ匂いが漂っていることに気付いて、仕方なくシャワー室に駆け込んだ。
超高速でがしがしと身体を洗って水気を拭き取り、ようやく游月の許に向かうことができたのだった。
分かってる。きっと今日会ったイラストレーターは、自分の個性をきつい香りの香水に託して身体に振りかけるような、そんな女性だったのだろう。長時間一緒にいれば、否応なく香りが移ってしまう。
襟元の口紅だって、ちょっとしたはずみで付いてしまっただけに違いない。こんな風に怒って癇癪を起こすなんて子供じみた真似をせず、落ち着いて質せばよかったのだ。でも、でも―――
「ショック……だったんだもの…………」
一人の夜は淋しくて淋しくて、それでも時計とにらめっこしながら透麻の帰りをひたすら待った。なるべく早く帰りますと言って出て行ったのに、何の連絡もないまま夜が更けて、耐え切れず透麻の匂いのするシャツにすがった。
そうやって何とか頑張って留守番していた自分を、女性の移り香をぷんぷんさせたまま抱こうとするなんて―――
「ぁ………」
ドアノブがかちゃりと回る音を耳にした游月は、咄嗟に布団を引っ張って寝たフリをした。
仰向けのまま目を閉じて耳を澄ますと、ひたひたと控え目な足音が近付くのが分かる。と同時に、石けんの清々しい芳香が漂って空間を満たした。
きっと大慌てでシャワーを浴びて、身体中をこすりまくったのだろう。そう思うと何だか透麻が可愛く思えて、全て許してあげたくなる。でも游月はじっと目を閉じて、わざとらしい寝息なぞをたててみた。
「游月……まだ怒ってますか………?」
―――怒ってるもん、すこしだけ
「寝てしまったのですか……?」
―――寝てるもん
答えは心の中で。そしてひたすら寝たフリを続ける。すると近くで空気が動く気配が。透麻さん諦めて寝るのかなと思った瞬間、耳もとを温かく湿った息が包み込んだ。
「ゆづき……許してください。愛してます………」
重厚な光沢のあるバリトンと甘い吐息の混交は、何物にも勝る媚薬。それを耳から注ぎ込まれた游月の躯は、あっという間にとろけて火照り始めた。
耳たぶ、頬、唇―――透麻の指が触れた部分は全て、紅く色づいて熱を帯びる。もはや寝たフリをしているのはバレバレだったが、半ば意地になっていた游月は目を開けようとはしなかった。
「ああ……眠っているあなたも美しい。食べてしまいたいほどだ………」
透麻はうっとりと呟きながら毛布を払って、游月の傍らに腰を下ろした。そして、
「どうやら起きる気配はなさそうですね。では、このままいただいてしまいましょう」
誰にともなく語りかけると、パジャマ代わりのゆったりしたシャツを大きく捲り上げて白く滑らかな胸を露わにする。そして薄闇の中で淡く色づく双つの果実を、指でくにくにと揉み始めた。
「っふ、ぅ……ン…………」
いきなりの刺激に游月は腰を軽く跳ね上げ、鼻にかかった喘ぎを漏らす。しかし目は依然として閉じたまま。
「ああ……硬く張ってきましたね。ぷちぷちして今にも弾けそうだ。では、弾ける前に食べてしまいましょう」
芯を持って勃ち上がった肉の実を口に含み、優しく歯を立てたと思ったら、舌先で押し潰し乳輪をぬるぬると舐め回す。もちろん、吸っていない方の胸も指先で嬲ることを忘れていない。
游月は「くふっ……」と喉の奥で悶えながらも、このじれったい愛撫に耐えていた。しかし、尖った乳首の先端を円を描くように指で撫でられながら、首筋から胸にかけてつつ…と舌を這わされると、たまらず腰を大きくひねった。
すると脚の付け根から、クチュ、と粘液がこすれる音が漏れ聞こえてきた。透麻は思わず会心の笑みを浮かべ、
「おや? 今の嫌らしい音は何でしょう。ちょっと確かめてみましょうか」
下着ごとするする脱がせて、あっという間に白い下半身を闇に晒す。
「おやおや、ここは眠っていなかったのですね。こんなに涎を垂らして」
その恥ずかしい事実を知らしめるように、わざと愛液を弾くようにして音を立てつつ、游月の半身をこすり上げる。
「んふっ……ふぁっ、ぁっ…………」
游月は頑なに目を閉じたまま、シーツに爪立てて嬌声を上げる。秘めやかな陰翳漂う媚態を賞翫した透麻は、真っ赤に膨れた先端を親指の腹で撫で回した。すると小さな孔からとぷとぷと新たな蜜が溢れ、透麻の手を濡らした。
「美味しそうな蜜だ。さっそく味わってみるとしよう」
蜜ごとつるりと口の中に含み、舌を絡めつつ吸い上げる。根元に指を巻き付けて扱きながらくびれの部分に歯を立てると、「やっ…」という小さな悲鳴と共に生温かい液体が口腔に溢れた。
透麻はそれを全て飲み干して、名残惜しそうに口を離した。
「んっ……ふ、ぅ……ぇ……ふぇ……………」
我慢しきれず透麻の口の中に放ってしまった游月は、恥ずかしさと罪悪感のせいか啜り泣きを始めた。
「ああ、游月の蜜は本当に美味しかった。ごちそうさまでした」
浮き立った声でそう言って、濡れた目尻にちょん、とキスを落とす。どうやら透麻はこのシチュエーションにハマってしまったようだった。
「まだ目を覚ましそうもないですね」などとわざとらしく呟きつつ、膝裏に手を掛けて脚を大きく割り開き、濡れた蕾を外気に晒す。
愛液や透麻の唾液が滴って、そこはまだ触れてもいないというのに、既に紅く膨れてひくひく蠢いていた。
「眠っていても游月のココはいやらしいのですねえ。まるで、熱帯の密林に咲く肉厚で淫らな花だ。きっと、奥はもっといやらしくうねっているのでしょうね」
透麻は両手の人差し指をつぷりと突き入れて、襞を捲り上げながら奥を探った。
「ああ、すごい……。紅い花びらが、指に絡みついて…………」
自分の恥ずかしい部分を覗き込まれている上、逐一言葉で描写されているのだ。游月はカッと燃え上がるような羞恥に耐えられず、両手で顔を覆った。
しかし透麻はますます勢いづいて、音をたてて掻き回す。お尻の奥から漏れるクチャクチャと咀嚼するような音は余りに卑猥で、游月はたまらず声を上げた。
「だめぇ………もう、ゆるして…………」
しかし透麻は何食わぬ顔で指をズポズポと出し入れしながら、
「可愛い寝言ですね」
愉しそうに言い放つ。そしてついに、逞しい指で奥のささやかな突起をぐり、と抉った。游月は「キャアッ」と嬌声を上げて腰を揺らめかせ、目を開けて哀願した。
「ああッ、あああ…ん……も…イヤアァ………きて、きてよぉぉ…………」
「おや? 起きていたのですか」
「い、今起きたのッ」
涙で濡れた双眸で、キッと睨みつける游月。対照的に、透麻は春風のように淡く柔らかな眼差しを向けて、
「そうですか。では、おはようございます。游月」
にっこりと微笑んで、游月の蜜でどろどろになった指を目の前に翳してみせた。游月は荒い呼吸で胸を波打たせながら、
「いやッ、透麻さんのいじわるっ。も、嫌い、だいっ嫌い!」
「傷付きますね。何故ですか?」
「だって嘘つきだものっ。早く帰るって言ったくせに、お土産持って帰るって言ったくせにっ。それに、それに―――」
しゃくり上げながら首を振る游月。あの香水の匂いは透麻が悪いわけではないのだから、言ってはいけないと自分を抑えているのだろう。
そんな游月らしい思い遣りも愛おしくて、感情の高ぶるまま顔中にキスの雨を降らせた。
「ん……とうまさぁん…………」
温かく柔らかな唇の感触に、游月の波立つ感情も次第に凪いでゆく。
「游月、許してください。あなたに嫌われたら、私は暗闇の中で迷ってしまう………」
睦言の延長だと分かっていても、やはり「嫌い」と言われるのは辛かった。
「ね、どうしたら許してくれますか?」
游月はゆったりと腕を伸ばして透麻の首に巻き付け、
「僕の……いやらしい花びらを虐めてくれたら許してあげる………」
「指で? それとも―――」
「指はいや……。透麻さんのおっきいのがいいの………」
透麻は下着を脱ぎ捨ててびちびちに勃ち上がった雄を見せ付けると、
「途中で眠らないでくださいね」
悪戯っぽく囁いて、游月のとろける花蕊にずぶずぶと埋め込んでいった。
「ね、游月。実は前からお話ししようと思っていたのですが、挿し絵を描いてみませんか?」
「え……挿し絵って何の………」
「もちろん、私の小説の、です」
游月はぽかんと口を開けて、純粋な驚きを露わにした。
透麻は優しく目を細めると、ついさっきまで腕の中で燃え上がり、情欲を際限なく揺さぶり続けた愛しい身体をそっと抱き締めて、
「あなたが前に見せてくれた絵。懐かしいけれどどこか物悲しい、夏の黄昏のような空気感が漂う世界が、どうしても忘れられないのです。
誤解されやすいのですが、私が本来書きたいのはグロテスクで頽廃的な耽美小説ではなく、現実の世界からほんの少し浮き上がった現代の寓話。ね、あなたの絵にぴったりだと思いませんか?」
游月は何と答えてよいか分からず、ただ頬を真っ赤にして透麻の胸にすり寄った。
「そんな風に感じてくれてたなんて……」
深い感慨を込めて呟く游月の頭をそっと撫でて、
「『幻想小説』の新刊に掲載されている短編小説、あれを読んで、游月の思うがままに描いてみてくれませんか?」
透麻の腕の中でこっくり頷いて目を閉じ、暗闇の中で想像の翼をはためかせた。
「榊先生、これは……」
「私は口出ししません。貴女の目で選んでください」
神谷女史の目の前にあるのは、2種類の絵。ひとつはこの前無理やり会食を開かせられた著名なイラストレーターのもの。そしてもうひとつは、透麻が黙って差し出した無名画家の作品。
どちらも、『幻想小説』に掲載されている透麻の短編をもとに描かれたものだった。しかし出来上がったものは驚くほど違う。
この小説は、現代に生きる吸血鬼の悲哀を淡々と綴ったものだった。
吸血鬼の女は恋人に正体を打ち明け、ほんの少しでいいから血を吸わせてくれと懇願する。彼女を愛している恋人は全てを受け入れて首筋を差し出すが、皮肉なことに恋人への愛が高まるにつれて欲する血の量も増えてゆく。
結局彼女は愛情の募るままに恋人を求め、その血を求め、恋人の命を奪ってしまうのだ。
神谷女史は表情を引き締めて、透徹した眼差しを二つの作品に注いだ。結論はすぐに出た。口許から鮮血を滴らせ、官能的な笑みを漏らす女吸血鬼を描いた著名イラストレーターの作品を指差し、
「誰が見ても、技巧的にはこちらの方が上だと思うでしょう。細部の描き込みや構図など、思わず目を惹かれてしまいます。でも―――」
透麻が持参したものをそっと手に取り、
「先生の小説に寄り添い、支えることができるのはこちらです。私見ですが、先生はあの話で、男の生き血を吸う女の魔性を描こうとしたのではない。愛すれば愛するほど相手に依存し自分を見失い、愛ゆえに破滅する女の悲哀を表現したのです。吸血鬼は主題ではありません」
透麻は嬉しそうに頷いた。
「その通りです」
「こちらの方は、それをちゃんと理解している。いえ、理解を超えて共感しています」
透麻が差し出した絵に描かれた女性は、少女めいて無垢な美貌に苦悩の翳を落として、それでも何かに憑かれるかのように、項垂れる恋人の首筋に吸い付いていた。
「この表情……胸が締め付けられます。これを描いた人は、愛の残酷さ、恐ろしさを知っているんだわ」
「そう、愛とは際限なき執着だということを」
神谷女史の感慨に透麻は昏い声で答える。しかしすぐ朗らかに笑って、
「では、秋に出る新刊の挿し絵はこちらの方に依頼するということでいいのですね?」
「ええ、もちろんです。お願いいたします。それで、この方のお名前は……」
「游月、です」
神谷女史は一瞬、大きく目を見開いて透麻を見上げたが、やがて瞳を輝かせて、
「やっと本物の游月さんに会えるのですね。やったあ」
游月の作品を大事そうに胸に押し当てて、にっこりと笑った。
(Fin)
BACK TOP INDEX