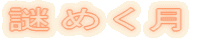
―80万ヒット記念SS―
1.
数多の古書店が軒を連ねる日本有数の古本屋街。メインストリートから少し離れた奥の脇道沿いにある珈琲店で、透麻は編集者を待っていた。
店の一番奥、擦り硝子の衝立に囲まれた特等席。昔はよく、ここにワープロを持ち込んで出版する当てのない作品を書き連ねたものだった。
お腹が空いたなと思うと、何も頼んでいないのにそっとオムライスやナポリタンが差し入れられる。気難しくて頑固だという評判の店主に何故か透麻は気に入られており、作品が認められるようになると我がことのように喜んでくれたのだった。
そんなコーヒー色の思い出に耽っていると、カランコロンという古風な鐘の音と共に待ち人が現れた。
「榊(さかき)先生。お待たせして申し訳ありません」
「いえいえ、時間通りですよ。私が勝手に早く来ただけですから」
透麻の担当編集者である神谷(かみや)女史は、まだ二十代半ばという若さながら、知識と情熱と誠実さで透麻の信頼を得ていた。
彼女は席に着くなり、何の前置きもなく次作のスケジュールや文芸雑誌『幻想小説』への掲載予定について説明し、透麻の了承を得たところで冷めたコーヒーを一気飲みした。
透麻は喉の奥で「くくく…」と笑い、
「相変わらずですねえ。生き急いでいるというか」
「はい、気分はもう還暦なんです。せっかちは死ななきゃ治らないと言いますか。あ、そうだ。忘れるところでした」
オレンジ色の鮮やかなバーキンの中から、葉書の束を取り出して、
「これ、読者カードお渡ししますね。不思議だわ。日頃から読者こそ最大にして最高の批評家だと触れ回っている大先生が目も通さず、榊先生のような孤高のイメージがある方がきちんと読まれているのだから」
「そういうことを言っていると、出世しませんよ」
神谷女史は肩を竦めて小さく舌を出した。かと思えばぐっと身を乗り出して、
「そうそう、最近先生のファンの間で、“游月の謎”が話題になっているってご存知でした?」
「いえ、初めて聞きました。それは―――」
「そうなんです。『月に游ぐ』の冒頭の献辞―――<我が最愛の游月に捧ぐ>。この<游月>とは一体誰なのか、先生のファンサイトで色んな憶測が飛び交っているようです」
透麻は読者カードに目を落とした。確かに、そこにも游月に関する控え目な質問が添えられているものがあった。
「ええ、そこにも書かれているでしょう? まあ読者が気にするのも仕方ないかもしれませんね。先生が作品に献辞を掲げるなんて初めてだし。しかも“最愛の”とくれば、下世話な想像を巡らせたくなるのでしょう」
「ほう。ちなみにどんな憶測が―――」
「色々ですよ。次作の登場人物の名前ではないかとか、先生が理想とする架空の読者の名ではないか、なんて。
そもそもこの献辞自体がメタファーなのだ、なんて意見もあります。私が游月です、と名乗りを上げる人まで。あと、先生が偏愛している人形の名前では、なんていうのも」
透麻は呆れると同時に感心した。
「なるほど、乱歩の『人でなしの恋』ですか。さすが私の読者だ」
「まあ、一番散文的で一番下世話で一番支持を集めている意見は、先生の恋人の名前ではないか、というものなのですが」
透麻は淡い笑みを浮かべて、「想像力の飛躍も現実的な思考には敵わないのですね」とだけ言い置いた。
唯一彼女にだけは恋人と一緒に暮していることを伝えてあったが、さすが女史は相手について一切詮索せず、この話題もこれで終わりとなった。
下らぬ世間話や文壇の噂話など透麻が好まぬことを知り尽くしている女史だったから、仕事の話が終われば打ち合わせも終了するはずだった。
しかし女史は、これまでと比べて明らかにトーンダウンした口調でおそるおそる言葉を継いだ。
「あの、もうひとつ……。先日お伝えした挿し絵の件なのですが―――」
彼女が語尾を濁すのは珍しいことだった。然もありなん。透麻はちらと眉を顰めて、
「そのお話はお断りしたはずですが」
ある有名な女性イラストレーターが透麻の熱狂的ファンで、挿し絵をぜひやらせて欲しいと言っている、そう聞いたのはほんの数日前のことだった。
透麻も彼女の絵は何度か目にしたことがあったが、レオノーラ・キャリントンやレメディオス・バロなど、有名な女性シュルレアリストの稚拙な模倣としか見えなかった。
それに、植物や人の顔を必要以上にグロテスクに描くのも、幻想や頽廃をこれ見よがしに誇張しているようで透麻は好きになれなかったのだ。だからその場で断りの言葉を差し出し、それでこの話は立ち消えとなるはずだったのだ。しかし、
「申し訳ありません。実は、先生のご意向を先方にお伝えしたところ、作品を見もしないで断るとは非礼が過ぎるとお叱りを受けまして。うちの雑誌にもよく作品を提供していただいているもので、余り無下にもできなくて」
「冷たい言い方かも知れませんが、それは私には関係のないことですね」
女史は力なく頷いて、
「仰る通りです。先生には何の関係もありません。私も、先生の作品に挿し絵なんて必要ない、寧ろ読者のイメージを限定してしまうから邪魔なのだとお伝えしたのですが、先方がどうしても一度自分の絵を見て、それから決めて欲しいと言って譲らなくて。単に先生に会いたいだけのようにも思えるのですが」
透麻は本名を出しているから覆面作家というわけではないが、写真はもちろん、プライベートを明かすようなプロフィールも皆無。
今や作家の大いなる収入源ともいえる雑誌のエッセイなども書かない上、神秘と怪奇の色濃い作風のためか、その謎めいた人物像に好奇の目が向けられて久しかったのだ。
グダグダ泣き言をこぼしても仕方がないと切り換えたのだろう、神谷女史は簡潔に用件を伝えることにした。
「それで、先生を交えて、一度会食を開きたいと考えております。もちろん私も参ります。その時、先生の口からきっぱり断っていただかないことには、先方を納得させるのは難しいかと」
透麻は腕を組んで、黙って女史を見つめるばかり。私がそういった場を嫌忌していることはご存知でしょう? と無言の圧力。女史はそれを正面から受け止めて、深々と頭を下げた。
「お願いします。その会食に先生を連れ出すことができないと、私は先生の担当を外されてしまうかもしれないのです」
透麻は溜め息をついた。編集者は幾らでもいるだろうが、彼女のような気質と才能の持ち主にはなかなか巡り会えないだろう。それに、長い付き合いで育まれた阿吽の関係を失うのは、透麻にとっても損失になる。
「分かりました。では、とにかく会食に出席だけは致しましょう」
「あ、ありがとうございます。先生ご本人から直接断られたら、さすがに先方も諦めざるを得ないと思います」
神谷女史は心底ほっとした表情で、テーブルの上の書類などを片付け始めた。透麻はふーっと少し大仰な溜め息を吐き出して、
「しかし私の作品が好きだからと言って、何故今になってそんな強引に……。理解に苦しみますね」
「何でも、運命を感じたそうです」
女史の答えは透麻をさらに困惑させた。女史は書類をまとめながら、ちらと上目使いで含みのある視線を送ると、
「先生ご存知なかったのですか? そのイラストレーター、ゆづきさんと仰るのです」
どうか字は違いますように、と、透麻は祈らずにはいられなかった。
「―――と、いうわけなんです」
神谷女史との話を細大漏らさず語り終えた透麻は、微かな疲労感を漂わせてソファの背に凭れかかった。
隣に座ってじっと耳を傾けていた游月は、そっと間を詰めて身体を寄せ、労わりを込めて頬にちょん、とキスをした。そして、
「厄介なことに巻き込まれてしまって………。透麻さんはただ、素敵なお話を書いて読んでくれる人に悦びを与えたいだけなのに」
透麻はふわりと微笑んで手を伸ばし、游月の肩を抱き寄せた。すると、游月は首筋に頬をすり寄せて甘えてくる。透麻はその顎に指を掛けて上を向かせ、半開きのふっくらした唇を優しく塞いだ。
游月は「んっ…」と鼻にかかった可愛い吐息をこぼす。ちゅ、と音をたてて唇を離すと、透麻の顔から疲労の翳はきれいに消えていた。游月はほっと安堵の息を漏らして、
「それで…その会食はいつなの?」
「明日の夜にしてもらいました」
「えっ…ずいぶん急なんですね」
「嫌なことは、早々に終わらせてしまいたいので」
キスのせいでほんの少し赤みを帯びた頬を、透麻は指でふわふわと撫でる。しかしその甘い仕草とは対照的に、眉根を寄せた苦しげな表情で、
「ですから、明日の夜は游月ひとりになってしまいます。大丈夫ですか?」
「ん、大丈夫です。少しさみしいけど……」
「ひとりでも、ちゃんとご飯は食べるのですよ。それからは戸締りはしっかりして―――」
游月は首を伸ばして、はぐっと透麻の耳たぶに噛み付き、
「もおっ、子供扱いして。たったひと晩くらいへいき…………ぁっ、ん」
透麻はお返しとばかりに、舌先を尖らせて游月の耳へねじ込む。そしてぬめぬめと嫌らしく動かしてじっくり舐め回した。
「ぁ………ふぅ…ン、もぉ……やぁ……………」
身体中が性感帯とも言える游月だったけれど、耳は特に無防備で弱かった。低音で囁かれただけで頭の芯がじわん、と痺れてしまうのに、こんな風にねっとり愛撫されたらもう………
「だめぇ……耳、だめ……なの…………」
透麻は最後に耳たぶをちゅるっと吸って、ようやく口を離した。しっとりと潤み始めた游月の瞳を上から覗き込んで、
「誰が子供なんですか? こんな……艶っぽい表情で私を誘ってくるくせに………」
「うそ……子供だって思ってるんでしょ………?」
そう言いつつも、唇の間から濡れた舌先をちらちら垣間見せて、深いキスを誘う游月。簡単に吸い寄せられた透麻は、誘惑の舌を追い駆けて絡め取り、きつく吸い上げて味わった。
「ん……んっ………ちょ…だい……とうまさん…の…………」
重ねた唇の隙間から、おねだりする游月。透麻はその求めに応じて、とろとろと唾液を注ぎ込んだ。んく、んく、と無邪気に喉を鳴らして飲み干すと、背中に回した手にきゅっと力を込めて、
「やっぱり……ひとりはさみしい………たったひと晩でも………」
「私もですよ……あなたと過ごす時間は、たとえ一秒でもかけがえのないひとときなのです………」
透麻が同じ感情を共有してくれたことが嬉しくて、思わず笑みがこぼれる。その天衣無縫の笑顔を透麻は眩しそうに目を細めて見つめ、愛しさを込めて鼻の頭にキスを落とす。そして、
「会食は、游月の大好きな中華料理だそうです。ちゃんとお留守番できたいい子には、折詰でお土産を持って帰ってあげましょう」
「もおっ、やっぱり子供扱いしてるッ」
たった今、艶めく眼差しで深いキスを誘ってきたのと同じ人物とは思えないほど、頬を赤くしてむくれる游月の仕草も表情もあどけない。
時には神秘的に、時には艶めかしく、時には明るく輝く月の揺蕩いに、自分が完全に溺れてしまっていることを透麻は痛感した。
腕の中に大人しく収まったまま膨れている游月を、あやすようにきゅっと抱き締める。すると胸に顔をうずめて掠れた声で、
「お土産いらないから………なるべく早く帰ってきてね…………」
透麻は甘い香りのする黒髪にそっと唇を押し付けて、
「はい。あなたのいない夜に、私も長く耐えられそうにありません……」
ぽつりと本音を呟いた。
高級中華料理店のVIP専用個室で紹介された女性は、なるほど、自分の個性に絶大なる自信を持っている女性、といった感じだった。少し太めの意志の強そうな眉、何とも形容し難い色の口紅。
神谷女史の紹介に合わせて軽く一礼すると、彼女はほとんど無反応でぽかんと口を開けて透麻の顔を見つめるばかり。すると神谷女史が業務用の声で、
「では、細かいお話は食事をしながら致しましょうか。先生、よろしいですか?」
「ええ、もちろんです」
初めて透麻の声を聞いた女性は、明らかにうっとりとした表情でふわふわと頷いた。
席に着いて料理が運ばれてきてからも、女性は透麻のプライベートに関する質問ばかりを浴びせて、一向に仕事の話をしようとはしなかった。
「先生のお名前は本名なのですね。素敵なお名前」
「ありがとうございます。ああ、そうだ。まだあなたのお名前を伺ってませんでした」
女性はくす、と笑って
「ゆづき、です」
「それは存じ上げておりますよ。姓の方は―――」
「ゆづきはゆづきです。それ以上でもそれ以下でもありません」
透麻は内心の溜め息を淡い作り笑いに変えて、
「どんな字を書くのですか?」
「もちろん、月を游ぐと書きます」
「なるほど」
透麻は横目でちらと神谷女史を見た。すると女史は表情は変えず、テーブルの下で許し乞うように両手を合わせていた。
「どうでしょう、ゆづきさん。そろそろ先生に作品を見ていただいたら」
女史の提案に素直に頷き、
「そうですね。では、クロークに預けてありますので取りに行ってきます」
席を立って部屋を出ていった。と同時に残った二人ははあ、と大きな溜め息をつき、
「どうやら彼女、先生のことすっごく気に入ったみたいですねえ」
「え、そうですか?」
女史はぽきぽきと音を立てて首を回し、
「ええ。最初紹介した時、ぼおっとして先生のこと見つめていたでしょう? きっと、こんな美形の男性が現れるなんて思ってもいなかったのでしょうね。美しく聡明で且つ謎めいた作家……彼女のような夢見る女性が一番好むタイプだわ」
「……すみません、何だか鳩尾の辺りがむずむずするのですが」
仏頂面の透麻に、女史はほんの少し厳しい視線を向けて、
「先生は、ご自分の存在が周囲に与える影響について無頓着すぎます。過小評価も、度が過ぎれば罪だと思います」
反論しようと口を開いた透麻を控え目な仕草で制して、
「ええ、確かに下らない話です。でも僭越ながらひとつだけ忠告させてください。彼女には気をつけて。………先生の恋人のためにも」
透麻は少なからず驚いた。彼女がこういったプライベートに踏み込んだことを言うのは、初めてだったからだ。それだけ本気で心配しているということなのだろう。透麻は忠告を素直に受け入れた。
「それにしても…彼女遅いですねえ。クロークに荷物取りに行っただけなのに」
しかしそれから間もなく、大きなプラスチックケースを抱えて戻ってきた。
「お待たせいたしました」
そして開けようした時、神谷女史の携帯が鳴った。ひと言詫びて出た途端、額を曇らせる。そして短い返答をして切ると、
「すみません、会社からだったのですが、何か要領を得なくて……。トラブルが起きたことは確かなようなのですが……」
「あら、戻らなくていいのですか? 私たちのことは気にしないでください」
ゆづきの提案に、女史は「そうですねえ…」と煮え切らない返事をして、透麻の方をちらと見上げる。二人きりにするのは何だか不安だったのだ。しかし、すぐ戻って欲しいという社からの要請も無視するわけにはいかなかった。
「先生、よろしいですか?」
「もちろんです。トラブルが大きなものでないよう、祈っていますよ」
そうして神谷女史は帰っていった。恐らく会社に戻った彼女は、トラブルなど起きていなかったことを早々に知ることになるだろうが。
「では、あなたの絵を見せていただいてもよろしいですか?」
女史がいなくなったせいで、この空間がより耐え難いものになっていた。さっさと成すべきことを終えて、游月の待つ家に帰りたい。しかし、
「ね、透麻先生。場所を変えませんか?」
明らかに声調が変わった。それだけではない、眼差しの色も、漂う空気の匂いも。透麻は眉間に深い皺を刻んで、
「申し訳ありませんが、仕事の時間を割いてここに来ているので余り長居はできないのです。もうそろそろ―――」
「だめです。もう少し付き合ってください。ずっとずっとお会いしたくて、やっと願いが叶ったのですから、簡単にはお帰ししません」
そして、まるでこの絵は人質だと言わんばかりに手元に引き寄せて、
「この上に夜景の綺麗なダイニングバーがあります。そこでゆっくり飲み直しましょ。ね?」
彼女は自分の立場というものを理解しているのか――透麻はすっとこめかみが冷えてゆく感覚に囚われたが努めて平静を装い、
「私には、あなたの絵を見る義務はありません。これで失礼します」
「さっきの編集者の方、先生のお気に入りなんでしょ?」
なるほど、彼女には気をつけてと言った神谷女史の正しさがようやく実感できた。透麻は立ち上がり、
「分かりました。行きましょう」
「ふふ、ごめんなさい。ゆづきは悪い子なの」
透麻は思わず、拳を握り締めた。
INDEX TOP NEXT